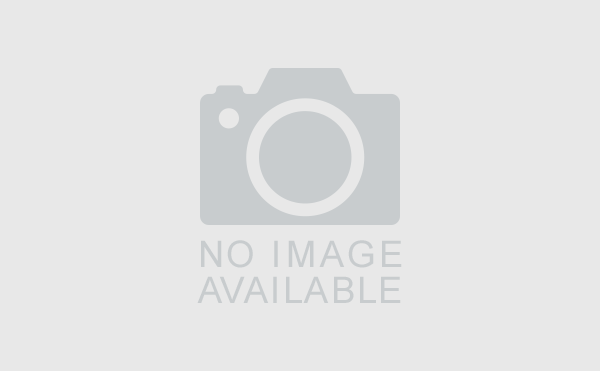No.170/DNRにつき、患者家族(キーパーソン)の同意があったか否かが争いとなった事案で、 医療機関側の主張が認められ、当該同意があったものと判断された事例 (東京地裁令和元年8月22日判決)
Table of Contents
No.170/2025.1.6発行
弁護士 永岡 亜也子
DNRにつき、患者家族(キーパーソン)の同意があったか否かが争いとなった事案で、
医療機関側の主張が認められ、当該同意があったものと判断された事例
(東京地裁令和元年8月22日判決)
1 事案の概要
平成26年10月2日、患者A(当時87歳)は自宅で呼吸苦が出現し、救急車でY病院に搬送され、そのまま入院しました。患者Aは、心不全の状態にあり、呼吸不全を併発して呼吸苦が出現したものと診断されました。患者Aの子X1・X2は、その日の夜、看護師から、患者Aの容態が急変した場合に挿管するか否かなどの治療方針について尋ねられましたが、もう一度考えてくるとして、返答を留保しました。 翌3日、Xらは、看護師から、急変時の対応について話し合って早期に決定することを求められるも、なかなか決断できないでいましたが、同日夕方の時点で、少なくとも、患者Aの容態が同日夜に急変した場合については、心臓マッサージ及びAEDは希望するが、人工呼吸器は希望しない旨、回答しました。また、Xらは、今後の急変時の対応について、Xらの話し合いで決まるまでは同じ方針で良い旨も回答しました。 同年11月7日、患者AはY病院を退院して自宅に戻りました。この間、患者Aの急変時の対応について、Xらが上記方針と異なる方針をY病院に伝えたことはありませんでした。 同年12月20日午前8時すぎころ、患者Aは自宅で呼吸苦が出現し、再び救急車でY病院に搬送され、心不全との診断で、Y病院に入院しました。この際、救急外来医師は、X2に対し、患者Aの病状について、呼吸不全によって状態がかなり悪いこと及び急変の可能性があることを説明し、患者Aの容態が急変した場合の延命措置について尋ねました。これに対し、X2は、前回入院においては人工呼吸器の装着を望まなかった旨を答えましたが、今回の入院後に急変した場合の措置については回答しませんでした。 主治医は、外来時の検査結果や前回入院の退院から約1か月半で再入院となったこともあり、患者Aの状態につき、前回入院時より悪化しており、肺水腫のため人工呼吸器による呼吸管理の適応もあるくらいのものと判断していました。そのうえで、患者Aの診察歴が短く、患者Aと十分な信頼関係が構築されるには至っていないことや、患者Aの同日の容態などに照らし、急変時の蘇生措置について直接患者Aに意思確認することは回避し、いわゆるキーパーソンと理解していたX2に上記措置について確認する必要があると判断していました。そこで、主治医は、X2への病状説明時に改めて、本件入院中の上記措置について回答を促しました。これに対し、X2は、患者Aに対する心臓マッサージ、気管内挿管などは行わないでもよいとする旨を答えました。これを受け、主治医は、電子カルテに「指示」として、「急変時 心臓マッサージ、気管内挿管などは行わない」との記載を入力しました。 翌21日午前1時28分ころ、患者Aに設置されていたモニターにより心停止が認められ、訪室した看護師が患者Aの呼吸停止も認めました。かけつけた当直医師らは、主治医の上記指示があったため、CPRを実施しませんでした。間もなくして、X2がY病院に到着し、患者Aに心臓マッサージが行われていないことについて疑問を訴えました。そのため、看護師が改めてDNRについて確認したところ、X2は、心臓マッサージはやってもらうようお願いしてあったと訴えました。しかし、当直医師が患者Aの病状について説明すると、X2は、「もっと早くに分からなかったんですか。」「あんなに元気だったのに」などと述べたものの、ひどく取り乱すこともなく、最終的に納得しました。その後、患者Aの家族がそろったところで、当直医師が患者Aの死亡を確認しました。患者Aの子Xらは、患者Aの急変時に心肺蘇生措置が実施されなかったことについて、主治医には、Xらから同意を得ずにCPRを実施しなかった注意義務違反があるとして、Y病院及び主治医を被告として、損害賠償を求める訴訟を提起しました。
2 裁判所の判断(東京地裁令和元年8月22日判決)
主治医は、Y病院の患者Aの電子カルテに、本件入院中の一連の指示事項の一つとして、「急変時 心臓マッサージ、気管内挿管などは行わない」との本件記載を他の指示事項の記載と同時に入力したことが認められる。そして、本件記載について、上記一連の指示事項の一つとして他の指示事項の記載と同時に入力されていることからすれば、主治医が他の患者への指示事項を誤って入力したものとは認められず、また、主治医が患者Aや家族の同意なしにそのような記載をあえて入力したということも想定しがたい。さらに、主治医が、何らかの事情で上記同意が得られたものと誤認して本件記載を入力した可能性は、抽象的にはないとはいえないが、憶測の域を出るものではない。 患者Aについては、前回入院時において、看護師からXらに対し、容態急変時の対応が尋ねられていたものであるところ、本件入院時においては、前回入院時よりも容態が悪化していたものといえ、急変の可能性は高まっていたといえるのであるから、Y病院の医師ないし看護師において、急変時の対応をキーパーソンとみていたX2に確認することは、ごく自然の成り行きであったと認められる。本件入院時の救急外来看護記録の病状説明内容欄に、「延命は?→息子)前回は人工呼吸器望まず。今回は?・・・」と記載されているのは、この成り行きに沿うものであり、この記載のようなやり取りが看護師とX2との間でされたものと認めることができる。 そして、救急外来段階で患者A急変時の対応に係るX2の意思が明確に示されなかったことについて、主治医に引き継がれなかったことをうかがわせるような事情は認められず、主治医は、その陳述書にも記載があるように、この点について引継ぎを受けていたものと推認される。 また、前回入院時からの主治医が、X2に対し、本件入院時の患者Aの病状について何ら説明しなかったとは考え難く、X2としても、主治医から何ら病状についての説明がないまま、救急外来での説明のみで満足したとは想定しがたい。 以上のような事情を考慮すれば、主治医は、本件入院に際し、X2に対し、患者Aの病状について説明するとともに、急変時の対応についても確認を求めたものと推認することができるといえる。本件記載について、DNRの方針を聞き取った相手方や状況の記載がないことは、この推認の妨げとなるものとはいえない。また、証拠によれば、主治医の担当患者でDNRの方針を採る者は相当数いると認められることや、本件記載については患者Aの死亡後1年以上にわたり記憶喚起の機会がなかったことからすれば、主治医が本件記載に係る具体的状況の詳細を記憶していないことについても、上記推認を妨げる事情とはいえない。 上記各事情からすれば、主治医は、X2から本件記載と同旨の回答を得て、本件患者の電子カルテに本件記載を入力したものと認められるというべきである。X2は、患者Aの容態が急変した旨の電話連絡を受けてY病院にかけつけた際、看護師に対し、患者Aに心臓マッサージが行われていないことについての疑問や心臓マッサージは依頼していた旨を訴えているが、その後のX2の発言内容その他の言動によれば、入院から1日も経過しないうちに患者Aの容態が急変したことに動揺したX2が、反射的に上記疑問等を訴えたものとみることができ、X2がこの訴えをしたことをもって、上記の認定を左右する事情とはいえない。 上記によれば、患者AのDNRについてはX2の同意があったといえる。そして、その余の事実関係も考慮すれば、患者Aの容態が急変した際にCPRを実施しなかったY病院の対応について、注意義務違反があると認めることはできない。
3 まとめ
本件事案では、DNR(終末期状態の患者で、心停止時に蘇生措置を行わないこと)につき、患者家族(キーパーソン)の同意があったか否かが争われました。 裁判所は、患者の容態急変の可能性が高まっている状況下において、医師が、急変時の対応をキーパーソンに確認することは、ごく自然な成り行きであるとしたうえで、診療録や看護記録の記載内容を基に、キーパーソンとの間で、その記載のとおりのやり取りがなされたことを認めました。そして、DNRにつき、キーパーソンの同意があったとして、医師の注意義務違反を否定しました。 しかしながら、本件事案では、患者の診察歴が短く、患者やその家族との信頼関係が十分に構築されるに至っていなかったという事情があり、そのことの影響もあるのかもしれませんが、CPRにかかる方針について、十分な話合いや意思確認がなし得ていなかったという状況がうかがわれます。現在拡がりつつあるACPの考え方に立てば、医療者はもっと患者家族(キーパーソン)に寄り添って、より丁寧に、その方針検討・意思確認を行うべきであったように思われます。 また、平成28年12月16日、一般社団法人日本集中治療医学会が、「DNAR指示のあり方についての勧告」を公表しています。同勧告では、「DNAR指示に関わる合意形成と終末期医療実践の合意形成はそれぞれ別個に行うべきである。」、「DNAR指示に関わる合意形成は終末期医療ガイドラインに準じて行うべきである。」、「DNAR指示の妥当性を患者と医療・ケアチームが繰り返して話合い評価すべきである。」、「心停止を『急変時』の様な曖昧な語句にすり変えるべきではない。DNAR指示のもとに心肺蘇生以外の酸素投与、気管挿管、人工呼吸器、補助循環装置、血液浄化法、昇圧薬、抗不整脈薬、抗菌薬、輸液、栄養、鎮痛・鎮静、ICU入室など、通常の医療・看護行為の不開始、差し控え、中止を自動的に行ってはいけない。」、「DNAR指示が出ている患者に心肺蘇生以外の治療の不開始、差し控え、中止を行う場合は、改めて終末期医療実践のための合意形成が必要である。」などの留意点が示されています。 本件事案は、当該勧告が公表される前の事案であるため、裁判所において、当該勧告の内容が考慮されるには至っていないようですが、もし当該勧告の内容に則った判断がなされたとすれば、果たして、医療機関側の責任を否定する結論に至ったのか否か、疑問なしとはしません。 そもそも、本件事案では、診療録や看護記録の記載内容を基に、医療機関側の主張が認められましたが、その記載内容は、 DNRの方針を聞き取った相手方や状況の記載がないなど、必要十分な情報がすべて記載されたものにはなっていなかったようです。医療者が、患者家族(キーパーソン)とともに、患者本人の価値観を尊重した意思決定・方針決定を行おうとする場合には、その話し合いの過程が重要になるはずです。したがって、いつ、誰と、どのような話合いをしたのかについては、できる限り記録に残しておくことが肝要です。忙しい臨床現場において、逐一詳細に記録に残すことは容易なことではないかもしれませんが、それでも、意思決定・方針決定の過程については、できる限り記録に残しておくことが、紛争予防・紛争解決の観点からも、非常に大切なことといえます。