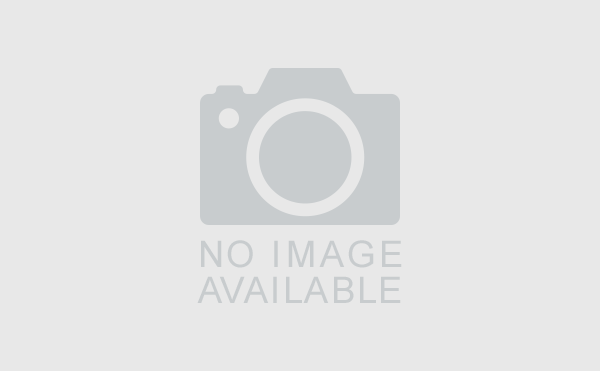No.169/裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その9 9.患者が不合理な治療法を選択した場合の医師の‶説得義務″
Table of Contents
No.169/2024.12.16発行
弁護士 福﨑博孝
裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その9
9.患者が不合理な治療法を選択した場合の医師の‶説得義務″
9.患者が不合理な治療法を選択した場合の医師の‶説得義務″
(1)はじめに
医師の説明により″患者が合理的な治療法を選択したとき″には何も問題はないのですが、″患者が不合理な治療法を選択した場合″には、「医師は、もう一度、具体的に各治療法の利害得失を説明して患者側に誤解がないか確認したうえで最終的な選択内容を再確認し、果たして患者が真意に基づいて″メリットがより多い治療法″を選択せずに″効果が劣る治療法″を選択したのかどうかを確認する義務を負っている」といわれています。すなわち、患者の自己決定権は尊重されなければならないとしても、「″標準的な治療法と異なる治療法を選択した場合″には、「患者の選択を無条件に受け入れるのではなく、医師の説明を患者がきちんと理解したかどうかを確認すること」が不可欠だといわれています。しかしそれでもなお、「患者が、″標準的な治療法″と比べると″治療効果あるいは副作用・合併症等の点で劣ることを知りつつ、なおその治療法を希望していること″が判明すれば、患者の選択を尊重して標準的な治療法を実施することを断念せざるを得ない」という結果もあり得るかもしれません。もっともこれも、医師が「最善の方法ではないにもかかわらず、患者が選択した治療法を必ず実施しなければならない義務を課されている」ということを意味しません。すなわち、最判平成13・11・27(乳房温存療法事件判決)が判示するように、「医師は、自らは胸筋温存乳房切除術が患者に対する最適応の術式であると考えている以上は、その考えを変えて自ら乳房温存療法を実施する義務はない」ということなのです。また、福井地判平成元・3・10もいう通り、「患者側が医師に対し一か八かの極めて成功率の低い手術の強行を求めることは、患者の自己決定権の適正な行使とは到底いえないし、さらにかかる要求に従わない医師ないし医療機関をして診療契約上の義務違反として問責し、損害賠償の責を負わせるごとき見解には…到底左袒できない。」ということなのです。 いずれにしても、医師は患者が不合理な治療法を選択しようとしているときに、″どこまで患者の意思に従わなければならないのか″、″どこまで説得すべきなのか″、あるいは″どこまで当該患者を説得することができるのか″が問題とならざるを得ないのです。
(1)宮崎地判平成6・9・12
この点については、宮崎地判平成6・9・12が参考になります。本判決は、脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血のため入院した患者の家族が、医師から「クリッピング手術が必要であるが、脳動脈瘤の発生部位からの出血の危険性が高いこと」などを説明されて、他の治療法を質問したところ、医師から「バイパス・頚動脈結紮術」を説明されたので、当該手術を受けることを選択し、2週間後に手術を受ける予定になっていたところ、その間に患者が昏睡状態に陥り、結局死亡するに至った事案に関し、医師が当初の説明において、「最適な手術方法を採用すべきこと」を十分説明しなかった点に説明義務違反が認められました。すなわち、本判決では、「医師は、医療の専門家として、患者の拒否等の特段の事情がある場合を除き、臨床的医療水準に従い、自己が最善と考える医療を行うべき義務がある。したがって、ある患者に対する治療法として第1と第2の二つの方法があるが、医療の実践の現場においては通常第1の方法が採用されており、患者の回復可能性の観点からしても第1の方法が優れ、医療現場における一般的評価も同様である場合に、当該医師自身も当該患者の治療法としては第1の方法が最善であると考えたならば、その治療法を行うことにつき患者側が直ちに賛成しなかったとしても、明確に拒否したのでない限り、治療行為の内容として、第1と第2の方法の利害得失を比較対照して具体的に説明し、患者側が的確な判断を行うことができるようにする法的義務がある。」と判示しています。もっとも、「上記内容の説明義務は、患者側で明確な拒否回答がない場合に限り肯定されるものであり、拒否している患者を説得すべき法的義務まで認めれるものではない。」とも判示している点も留意しておく必要があります。要するに、患者の自己決定権の一部として「治療法の選択権」を有することは当然のことですが、自己決定権を正しく行使するためには、各治療法について正確な情報が提供され、患者自身が合理的に判断できる状況がつくられていなければなりません。そのためには、医師が、患者に各治療法の利害得失について正確な情報を提供しなければならない義務を負っているということになり、しかも、その情報を提供した内容を患者が理解しているかどうか(提供した情報を誤解していないか)などについても確認しなければならないということなのです。
(2)東京地判平成18・10・18
また、この点については、患者が自己の病状を誤解し突然死の危険性があるにもかかわらず、入院せずに稼動し続けている場合において、担当医師には突然死の危険を告げるなどして誤解を解き強く入院精査を勧めるべき義務があると判示し、医師に対し説得義務を求めた裁判例(東京地判平成18・10・18)があります。この事案は、患者Aが労作時に息切れがするようになり、開業医Bを訪れ、肝腫大が認められたことから、同医師の紹介によりY大学付属病院外科を受診して検査を受けたところ、心疾患の疑いがあるとされたことから、同病院内科で数回にわたり同科教授である担当医師Cの診察を受けたものの、最終受診日の1週間後、患者の容態が急変し、大動脈弁閉鎖不全症及びうっ血心不全により死亡したというもので、Aの妻XがY病院を被告として損害賠償請求したものです。まず、この東京地判では、「患者は、人格権の一内容として、自己の行動について自ら決める権利を有しているから、特定の治療を受けるに当たっても、当該治療の性質、それによる効果、自らの身体状態等に鑑み、自ら納得の上で当該治療を選択するか否かを決すべきものであるところ、当該治療により予測される結果や治療による不都合は、専門的知識がなければ正確には認識できず、医師から説明されない限り、患者が知り得ないのが通常である。したがって、治療を行う医師としては、患者に対し、治療を受けるべきか否かを判断するのに十分な情報を説明すべき義務があるというべきである。そして、それを前提とすると、患者は自らの身体状態や必要な治療に対する評価について誤認をすることも多分にあるといえるところ、患者がこのような誤解をしていると医師が予見し得る場合においては、医師は、人の生命及び健康を管理する職責を有していることに照らし、患者の誤解を解くために十分な説明をする義務がある。」と判示しています。そして、その上で、「患者Aは大動脈弁閉鎖不全状態(AR)及びうっ血心不全の状態にあり、しかも、いつ死亡してもおかしくない状態にあったものであるところ、患者AのようなAR及びうっ血心不全の患者に対する治療を行うには入院精査が必要であった。医師Cも、そのような認識の下に、患者Aに対して入院精査の必要性があると述べた。しかしながら、…患者Aは、自らが心臓に疾患を抱えているとの認識こそあれ、その疾患がそれほど重大なものではないとの認識を有し、これを前提として自らの仕事を休むわけには行かないとの認識の下、医師Cが示唆した入院を拒否していたものと推認できるが、これは自己の病状の重大性に関する誤認から形成されたものと認められる。」と判示し、さらに「このように誤解によって自己の病状を正確に認識していない患者の治療に当たる医師としては、まず患者の誤解を解く必要があり、医師Cは、患者Aが自己の病態について正確に認識しておらず、その誤解に基づき、仕事が多忙であることを理由に入院を拒否していることを容易に認識し得た。そうすると、医師Cは、遅くとも平成12年8月5日の診察日までの時点において、患者Aに対して同人の病態を正確に説明した上で、夏休みなどに一時的にでも入院することを提案し、仕事が多忙であることを前提としても治療が可能になるように工夫し、とにかく入院を実現させるよう説得することが必要であった。しかしながら、医師Cは、患者Aに対して突然死の危険がある旨説明したとは認め難い。また、単に抽象的に入院精査の必要がある旨告げたにとどまり、その期間を告げることもなく、まず短期間の入院を勧め、その入院期間中に入院の継続を説得しようという試みもしていない。さらに、そのことを紹介者である開業医Bや患者Aの妻Xに告げて、患者Aの誤解を解くための協力を求めることもなかった。…しかも、医師Cは、最終診察日には最終的には経過をみるとの判断をして診察を終えているが、このことは患者の誤解を助長する積極的な過失行為といわざるを得ない。…医師Cは、もはや自己の考える医療行為が実現できないことは十分に認識しえたはずであり、そうである以上、その時点でその旨を明示し、自己の方針に従うか、他医への転医かの選択を求めるべきであり、それをせずに漫然と経過観察を続けることは、患者の誤解を解かなかったばかりかむしろ患者の誤った認識を是認し、その誤解を助長するものといわざるを得ないのであり、この点において医師の注意義務に積極的に反する行為であるといわざるを得ない。」と判示してY病院の医師Cの責任を肯定しているのです。
(3)福岡高判平成19・5・24
福岡高判平成19・5・24は、冠状動脈バイパス手術を受けた患者が術後に腸管え死の発生している可能性が高いと診断して直ちに開腹手術を実施していればその死亡時に死亡することはなかったとして慰謝料の支払が認められた事例ですが、ここでは次のように判示しています。すなわち、「丙川医師としては、平成3年当時においても、開心術後に腸管え死が生じる危険性があることを十分認識した上、その認識を踏まえて的確な診断をして、被控訴人らに説得力のある説明をすることが期待されたのである。また、仮に当時の医学水準からして、その機序を正確に認識することが困難であったとしても、少なくとも午前8時ころには、太郎の症状からして腸管え死を疑うほかない状況に立ち至ったのであり、しかも、腸管え死の場合には、直ちに開腹手術を実施し、え死部分を切除することが急務なのであるから、丙川医師の被控訴人らに対する回復手術の必要性についての説明・説得も当然そのような認識を踏まえたものでなければならないはずである。…そうすると、単に、被控訴人らが開腹手術に拒否的であったとか、午前8時ころにおいて開腹手術に対する被控訴人らの同意を得ることが困難であったというだけでは、太郎の主治医としての丙川医師の責任を不問に付すわけにはいかない。以上のとおり、丙川医師としては、午前8時ころには太郎の腸管え死を疑うべきであったとすれば、速やかにそのことを被控訴人らに告知し、それが死に直結しかねない重大な事態であること、したがって、直ちに開腹手術を実施し、え死部分を切除するほか救命の可能性はないことを十分に説明して、開腹手術への同意を得るように努めるべきであったし、このような説明・説得がなされてもなお被控訴人らが開腹手術に同意しないということは考え難いことである(現に、被控訴人らは、結局は本件開腹手術に同意しているところである。)。」というのです。
(4)大阪地判平成19・7・30
大阪地判平成19・7・30も説明・説得義務を肯定し、「医師Y1が、亡AにC型肝炎ウイルス検査を勧めたところ、亡Aがこれに従わなかったとしても、人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医師が患者の検査拒否を安易に受け入れることは相当でない。すなわち、医師Y1は、検査を拒否する亡Aに対し、改めて、C型慢性肝炎を発症しているとすれば、その予後がどのようなものとなり、それを回避するためにどのような治療が必要であるかを説明し、C型肝炎ウイルス検査を受検するよう説得を試みる義務(説明・説得義務)を負うというべきである(なお、説明・説得義務が尽くされても検査拒否の態度が変わらない場合には、それ以上に検査を実施する義務があるといえないことは当然である。)。」と判示しています。
(5)東京高判平成22・7・7
東京高判平成22・7・7も、「医師は、患者との診療契約(準委任契約)に基づき、専門家としての医療水準に従い、患者の利益のため自ら正当と考える医療を行う義務を負うものであり、その判断が患者の選択に拘束されるものではない。そして、正当な医療については、むしろこれを患者に″説得″することが同義務に基づいて求められるものといえるから、呼吸困難の原因が気道狭窄にあり、気道閉塞による窒息の差し迫った危険性があるとの前提を受け入れようとせず、不合理な対応に終始する控訴人(患者)に対し、被控訴人(医師)が、医学的見地から、亡Cの呼吸苦を緩和する措置に同意するよう強く説得をすることは、亡Cとの間の診療契約の趣旨に沿うものといえ(る)」と判示し、正当な医療についてはむしろ患者を説得することが求められるとしています。
(6)東京地判平成25・8・8
患者に不合理な選択をさせないようにするために、医師には積極的な説明(説得)が必要だとしても、例えば逆に、患者に手術を受けてもらうために、合併症のリスクなどについて正確な説明を避ける(比較的安全な医療行為であるかのような)説明をし、それをそのままにしておくことには問題があります。この点について、東京地判平成25・8・8は、脳動脈奇形摘出術を受けた患者に左片運動麻痺等の障害が残遺した事案において、「一般的に、医師が、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、特段の事情のない限り、患者に対し、手術合併症の危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容、利害得失及び予後等について説明すべきと解される。Y医師は、当初は、Xらがこれまで手術ができないと脅かされてきたことから元気づけるために、Xらに対して、手術には100%の自信があり、手術後2週間で退院出来る旨説明しているところ、本件手術には、後遺症が合併する危険性が相当程度存在しており、Y医師自身も認めるように、各種検査の結果、本件手術は相当困難であり、AVM全部は摘出できない可能性があると認識していたのであるから、このような当初の説明では、本件手術の危険性ではなく、むしろ安全性を過度に強調したものとなっており、Xらに対して誤解を与えかねない説明であったということができる。…そうすると、Y医師らは、本件手術の危険性について、Xらの誤解を解消するためにも、事後的に、通常より慎重な説明をする必要があったというべきである。…Y医師らは、本件手術の危険性について、自らの説明によって生じたXらの誤解を解消するためにも、事後的に、通常より慎重な説明をする必要があったというべきであるにもかかわらず、この点を意識した説明がされたことを認めるに足りる証拠が何ら存在しないことは、本件において、特筆すべき点いうべきである。」と判示しています。
(7)東京地判平成元・3・13
また、説得義務と関連するものとして、医師の注意義務として、患者の″受診中止(ドロップアウト)″に対する何らかの対応(説得等)が求められるか否かが問題とされる場合もあります。すなわち、患者が医師の受診を中止した場合に、医師が患者に対し、「受診中止の原因を突き止めて適切な助言をして病状の悪化を防止すべき注意義務があるか否か」について判断した裁判例(東京地判平成元・3・13)があります。この判決は、「Yは、Xの唯一の主治医として、初発がんの発生当初からがん再発に至る約7か月にわたってその治療に当たっていたものであり、しかも、その根治療法として未だ臨床上確立されていなかったプレオマイシンの局注療法を採用していたことが認められ、他方Xの再発がんを放置すれば、その性質上重大な結果を招来することは明らかであるから、右事実にかんがみると、Yとしては、XがYの治療を受けることを止めた後においても、Xが何故に受診を止めたのかをつきとめ、Xが適切な治療を続けていけるかどうかを確認し、適切な助言をして、病状の悪化を防止すべき注意義務があったというべきである。」と判示しています。もっとも、本件事案は、「Yに対し『先生治るんでしょうか』と尋ねたところ、Yは、確答することはできないと無愛想な返答をしたため、Yに対する信頼関係を失い、以後、Yの診療を受けることを止めた」という特殊な事情があったことは念頭に置いておく必要があります。
(8)東京地判平成20・7・31
上記(7)の東京地判平成元年・3・13とは逆の結論となった裁判例もあります。すなわち、CT画像上肝細胞癌の可能性が否定できなかったため、患者亡A(韓国人)に腹部エコー検査を実施し、その後亡Aが当該腹部エコー検査の結果を聞くための受診をしなかった事案において、亡Aの相続人Xらが「医師が高度の説明義務を尽くした上で、なお患者が受診を拒否した場合に限り、受診懈怠を理由として注意義務違反が否定されるけれども、本件では説明義務が尽くされていないから、受診懈怠を理由として、Y医師の注意義務違反が否定されることはない」と主張したところ、東京地判平成20・7・31は、「Y医師は、亡Aに対し、肝細胞癌のスクリーニングのために検査等を実施していることを説明していたものと推認されることに加え、韓国語の通訳が可能なB看護師の立会いの下、本件CT画像上肝細胞癌との確定診断はできないが、肝癌を否定できない気になる影があり、念のためにエコー検査をするなどと説明されていることが認められ、このような説明がなされた場合、その説明を受けた患者は、腹部エコー検査の後、主治医から検査結果を聞くために速やかに当該病院を受診するのが通常であるというべきである。そうすると、Y医師の亡Aに対する説明が、肝細胞癌が疑われる患者に対して受診を促す説明として不十分なものであったということはできない。」と判示し、上記東京地判平成元・3・13と逆の結論となっています。
(9)大阪地判平成25・2・27
もっとも、これらの事案に対し、医師がさらに強く説得したためにその説得の適法性・妥当性が争われた事例があります。すなわち、患者遺族から、「治療行為(抗がん剤の投与)についての医師の強引な説得が患者の自己決定権の侵害に当たる」として、医師らが損害賠償請求を受けた事案です。その点について、大阪地判平成25・2・27は、「抗がん剤治療を受けるか否かの最終的な選択は亡A女に委ねられているとしても、抗がん剤治療を受ける方が適切であるとの意見を有している主治医において、その意見を述べ、これに基づき抗がん剤治療を受けるよう説得することは、何ら非難されるべきことではなく、自分の家族であれば抗がん剤治療を勧めると言ったのになぜ抗がん剤治療を受けないのかと質問したからといって、これが違法であるとか不当であると評価することはできず、その表現が『私の家族だったら絶対に打つ。どうして抗がん剤治療を受けないのか』というものであっても、このことは同様である。」と判示し、医師らの責任を否定しています。そして本判決は、これに続けて、さらに、「自己の担当する患者が抗がん剤治療を受けないという選択をした場合に、その理由を聞くことは、主治医として適切措置であるし、亡A女の説明した理由が経済的な理由であったことから、医療費の減免制度を教示し、その担当者を紹介したことも、亡A女のことを考えての適切な処置であったというべきである。」と判示しています。