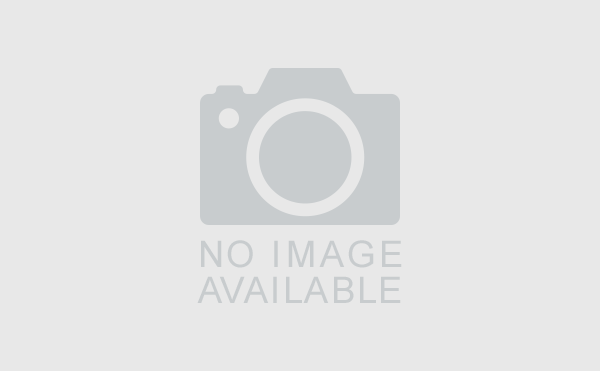No.177/家族が自宅での看取りを希望していた患者について、訪問看護施設の指示により、 救急搬送のうえ心肺蘇生がなされたことについて、訪問看護施設に対し損害賠償請求がなされた事案(棄却) 〜大阪地方裁判所・令和5年12月8日判決〜
Table of Contents
No.177/2025.8.1発行
弁護士 福﨑 龍馬
家族が自宅での看取りを希望していた患者について、訪問看護施設の指示により、
救急搬送のうえ心肺蘇生がなされたことについて、訪問看護施設に対し損害賠償請求がなされた事案(棄却)
〜大阪地方裁判所・令和5年12月8日判決〜
(はじめに)
本件は、患者の相続人である二男が、自宅での看取りの希望を訪問看護施設に伝えていたにもかかわらず、施設の看護師の指示によって救急搬送がされ、病院で心肺蘇生が実施されたうえで、救急搬送先で死亡したという事案です。亡Aの二男は、訪問看護サービス契約が締結された際、亡A、主治医及び訪問看護ステーションを運営する会社との間で、亡Aの終末期の最終段階における医療・ケアは、在宅での看取りによるとの合意があり、訪問看護ステーションの看護師には、救急活動を要請するかの判断を仰ぐため、亡Aの主治医に連絡する義務があったのに、これに反して救急車を呼ぶよう指示し、亡Aは在宅での看取りを受けられず死亡したと主張して、訪問看護ステーションを運営する会社に500万円(亡Aの慰謝料1000万円の法定相続分2分の1相当額)の請求をしました。 看取り等の終末期医療にかかわる裁判では、終末期における延命治療を実施しなかったことが違法であるとして、患者家族と医療者側で裁判になることがたびたびあります。その場合、医療者側の責任の有無の判断に際しては、厚生労働省が策定している「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」沿って医療行為の開始・不開始が判断・決定されているかが重要となります(本臨床医療法務だよりNo.23、東京地方裁判所平成28年11月17日判決等)。一方で、本裁判では、延命措置を実施したことが違法であるとして、患者家族が訴えており、今まであまりない事例となりそうです。
1 大阪地方裁判所・令和5年12月8日判決
(1)事案の概要
亡Aは、寝たきり全介助の状態となり、平成31年3月からG医師の訪問診療が開始されました。令和2年1月6日付け訪問看護指示書では、亡Aについて、寝たきり度B2、認知症の状況Ⅳ、要介護認定の状況5と判定されていました。亡Aの二男(以下「X」という。)は、G医師に対し、在宅医療を依頼した当初、亡Aについて自宅看取り希望である旨を伝えました。また、Xは、診察に同席した際、G医師に対し、新聞記事を提示して、孤独死で警察が来るようなことは避けたい、そのためにも在宅医療や訪問看護を利用していると話したことがあったとのことです。 訪問看護ステーションを運営する株式会社(以下「Y」という。)は、亡Aを担当していたケアマネージャーから、亡Aの褥瘡の対処のため、訪問看護に加わるよう依頼されたことから、亡Aとの間で訪問看護サービス契約を締結することとなり、令和2年1月6日、Xを代理人として、訪問看護サービス契約を締結しました。本件契約の内容は、Yの看護師が、週1回の割合で、亡A宅を訪問し、亡Aの状態観察、服薬管理、保清、創処置を行うというものでした。 亡Aは、令和2年5月18日当時、大阪市の自宅において、Xの妻の父と同居していました。Xの妻の父は、令和2年5月18日午前8時53分頃、Yに雇用されているE看護師に電話をかけ、E看護師に対し、亡Aが口から泡を吹いて反応がない旨告げました。E看護師は、同日午前8時53分、Xの妻の父から、亡Aが声掛けに反応がなく、口腔内が泡でいっぱいである旨の連絡を受けました。E看護師は、管理者であるF看護師及びM看護師と相談しましたが、看取りについて最終確認もできておらず、亡Aの詳細な状況も不明であったため、救急要請すべきという結論になり、Xの妻の父に対し、救急要請をするよう指示しました。
E看護師は、Gクリニックに電話をかけ、主治医であるG医師に対し、Xの妻の父から、亡Aが泡を吹いて反応がないとの連絡が入ったので、救急要請してもらった旨述べたところ、G医師は、E看護師に対し、亡A宅に向かうよう指示し、E看護師は亡A宅に向かいました。E看護師が亡A宅に到着すると、既に救急隊が到着しており、消防法に基づく救急活動として心肺蘇生が実施されており、E看護師は、G医師に再度連絡し、既に救急隊が到着して心肺蘇生が実施されていることを伝えました。その直後、E看護師は、Xに架電し、亡Aに心肺蘇生が実施されておりI病院に搬送予定である旨伝えました。亡Aは、その後、I病院に救急搬送され、同日午前11時4分に死亡しました。
(2)裁判所の判断
ア DNARについて
DNARは、心停止時に心肺蘇生を実施しないことを意味し、医師の指示によってなされる。もっとも、一般社団法人日本集中治療医学会倫理委員会は、事前指示という観点から、事前指示及び終末期医療の教育を受けていない医療従事者が患者の事前意思を十分に汲み取れずに、事前指示の画一的運用を行う可能性があるとの懸念から、日本における現状を考慮すると、DNARは患者及び家族と医師をはじめとする医療従事者(医療・ケアチーム)が最善の医療とケアを作り上げるプロセスを通じて合意形成に至ることが望ましく、医師の指示ではなく合意形成結果を関連する全ての人々が共有するものと捉えるべきであるとしている。
イ 一般社団法人日本集中治療医学会「DNARの在り方についての勧告」
一般社団法人日本集中治療医学会は、平成29年1月に採択した、DNAR指示のあり方についての勧告において、①DNAR指示は心停止時のみに有効である、②DNAR指示と終末期医療は同義ではなく、DNAR指示にかかわる合意形成と終末期医療実践の合意形成はそれぞれ別個に行うべきである、③DNAR指示にかかる合意形成は終末期医療ガイドラインに準じて行うべきである、④DNAR指示の妥当性を患者と医療・ケアチームが繰り返して話し合い評価すべきである、⑤Partial DNAR指示(心肺蘇生の一部のみを実施する指示)は行うべきではない、⑥DNAR指示は、日本版POLSTの「生命を脅かす疾患に直面している患者の医療処置(蘇生処置を含む)に関する医師による指示書」に準拠して行うべきではない、⑦DNAR指示の実践を行う施設は、臨床倫理を扱う独立した病院倫理委員会を設置するよう推奨する、としている。
ウ 厚生労働省作成(平成30年3月改訂)「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(終末期ガイドライン)
終末期ガイドライン、人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定について、患者本人の意思が確認できない場合には、①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする、②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とし、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う、③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする、④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする、という手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある、としている。
エ E看護師に、亡Aの急変時にDNAR合意に基づきまずG医師に連絡する注意義務の違反があったかについて
Xは、本件契約時に、X、G医師及びYの間で、亡Aの終末期において蘇生処置拒否であることを告げて、DNAR指示を含む合意がなされた旨主張する。しかし、前記認定事実によれば、本件契約締結の際、Xは、Yに対し、亡Aについて「在宅での看取り」を希望する旨を述べ、Yはこれを了承したことが認められるが、「在宅での看取り」が当然にDNARと同義あるいはDNARを含むものとはいえない。かえって、前記認定事実によれば、本件契約締結の際、Xは、Yに対し、亡Aについて、いかなる場合であっても心肺蘇生処置を拒否することや、いかなる場合であっても救急要請をせず、必ず主治医であるG医師に先に連絡することなど、DNARやこれに関する具体的な希望までは伝えていなかったことが認められる。 また、前記認定事実のとおり、本件契約締結時に、主治医であるG医師からYに対してDNARに関する指示はなく、DNAR指示に関する書面も作成されていない。そうすると、本件契約締結の際に、X、G医師及びYの三者間で、DNAR指示を含む合意がされ、これが本件契約の内容となっているとは認め難い。 これに対し、Xは、令和2年1月6日、Yとの間で、亡Aが急変した場合に救急要請をしない、心臓マッサージやAEDなどの心肺蘇生措置をしないとの内容を含む合意がなされていたと陳述、供述する。 しかし、前記のとおり、Xは、本件契約時に、Yに対し、いかなる場合も救急要請をしないことや、救急要請の前にG医師に必ず電話をすることなどを明示しなかったこと、また、主治医であるG医師に上記内容を伝えていなかったことを認めており、G医師に対して蘇生拒否を伝えたとのXの主張と整合しない。この点を措くとしても、Yの24時間連絡記録には、本件契約の翌日である令和2年1月7日の欄にDNARに関する記載はなく、かえって、Xに対し、亡Aの今後については在宅看取りを希望していることを確認したが、食事について、今後取れなくなった時に胃瘻をするかどうかまだ悩んでいる旨の記載があり、Xが、同日時点で心肺蘇生措置をしないことを決意し、Yとの間でその旨合意していたとは考えられない。したがって、亡Aが急変した場合に心肺蘇生措置をしない旨の合意があったとのXの陳述、供述は採用できない。・・・したがって、X、G医師及びYの間でDNAR指示の合意形成があったとは認められないから、E看護師に、令和2年5月18日当時、救急要請の前にG医師に連絡をする義務があるとは認められず、Xの主張は採用できない。
2 まとめ(解説)
患者やその家族が看取りの意向を有する場合、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の理念に沿って、医療・ケアチームは、本人の意思を尊重するため、本人のこれまでの人生観や価値観、どのような生き方を望むかを含め、できる限り把握し、また、話し合いが繰り返し行われたうえで、延命措置に関する方針を決定することが重要です。本件では、訪問看護サービス契約を締結して、4か月程度しか経過していない時点で、患者が急変し死亡するに至っていますので、時間的制約があったのかもしれませんが、終末期ガイドラインに照らすと、看取りを希望する患者に対して、話し合いが不十分であったのではないかという懸念は拭えません。しっかりと、方針を話し合い、書面で話し合いの内容を残しておくことが必要であったと思われます。 本裁判例は、ガイドライン等を検討したうえで、そもそも、「救急要請や心肺蘇生はしないとの合意まではなかった」として、患者家族からの請求は棄却されています。一方で、仮に十分、本人との話し合いがなされ、DNARを含む、延命措置の不開始について合意されていたにもかかわらず、延命措置が実施された場合の責任については判断していません。エホバの証人の輸血拒否事件(本臨床医療法務だよりNo.35、最高裁平成12年2月29日判決)では、「患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。」と述べて、患者の救命のための医療行為であっても、意思に反する輸血の実施について違法性が認められています。これを前提とすると、延命措置を実施しないことについて、患者の真摯な意思表示があり、ACPも実施したうえで、延命措置不実施の方針が決められたにもかかわらず、延命措置が実施された場合には、違法性が認められる可能性もあり得ると思われます。