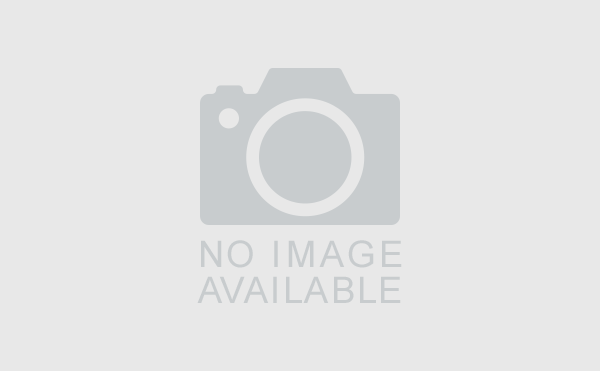No.175/東京都立広尾病院事件(最高裁平成16年4月13日判決) ~医師法21条の異状死体の届出義務と虚偽有印公文書作成罪~
Table of Contents
No.175/2025.6.2発行
弁護士 福﨑 龍馬
東京都立広尾病院事件(最高裁平成16年4月13日判決)
~医師法21条の異状死体の届出義務と虚偽有印公文書作成罪~
(はじめに)
本稿では、医師法21条の異状死体の届出義務について「異状死」の解釈や、届出義務の合憲性が争われたことで有名な都立広尾病院事件の地裁判決と最高裁判決をとりあげたいと思います。都立広尾病院事件で最高裁は、異状死体の届出義務について、いわゆる「外表異状説」をとったとされています。医師法21条は、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」と定めており、違反した場合には、50万円以下の罰金刑も規定されています。これについて、都立広尾病院事件で最高裁が採用したとされる「外表異状説」とは、死亡に至る経過等にかかわらず、外表に異状がある場合を医師法21条に定める「異状」であると解する説です。学説上は、強い批判がありはしますが、一応、最高裁は、外表異状説を採用していると解釈されることが多いようです。 また、本判例では、死亡診断書に虚偽の記載をしたことについて、虚偽有印公文書作成罪の成立を認めており、この点も、参考になる判断を示していますので、これに関する事実関係や判旨についても引用のうえ解説します。以下では、裁判所の判断を見ていきますが、控訴審(第二審)は、第一審とおおむね同様の判断がなされているため、控訴審の判旨の引用は割愛し、第一審と最高裁の判決を引用します。
1 事案の概要
(1)異状死の届出義務に関する事実関係
被告人(以下、「院長X」という。)は、医師であり、東京都渋谷区・・・所在の東京都立広尾病院(以下、「本件都立病院」という。)の院長として、患者に対する医療行為に自ら従事すると共に、同病院の院務をつかさどり、所属職員を指揮監督する等の職務に従事していました。慢性関節リウマチの患者Aを診察したところ、リウマチは長年にわたるものであり、病状は落ち着いているが、左中指が腫れていたので、院長Xは、その部分の滑膜を切除する手術を勧め、患者Aは手術を受けることとしました。院長Xは、同病院整形外科医師C(以下、「医師C」という。)を患者Aの主治医として指示しました。その後、平成11年2月10日に、主治医である医師Cの執刀により左中指滑膜切除手術を受け、手術は無事に終了し、術後の経過は良好でした。 翌11日、看護師が、患者Aに対し血液凝固阻止剤ヘパリンナトリウム生理食塩水(以下「ヘパ生」という)と消毒液ヒビテングルコネート液(以下「ヒビグル」という)を取り違えて投与(以下「本件事故」という)した結果、患者Aが死亡しました。翌12日に行われた病理解剖の結果、おそらくヒビグル投与により急性肺血栓塞栓症が生じ、心不全に至り死亡したとされました。病院長である被告人は、本件事故翌日(平成11年2月12日)の会議では、警察へ届出を行うとの判断をしましたが.監督官庁の東京都に相談したところ消極的な意見が出されたため、同日は届出をしませんでした。 同月2月20日、院長Xは副院長らとともに、患者Aの夫の自宅に、それまでの経過について中間報告をしに行きましたが、その席において、夫から、同人らが撮影した、患者Aの遺体の右腕の異状着色を写した写真を示され、事故であることを認めるよう詰め寄られ、病院の方から警察に届け出ないのであれば、自分で届け出る旨言われました。そこで、被告人は、帰り道に、同行した病院関係者らと話し合い、警察に届け出ることに決め、同日に東京都衛生局長らと面談してその旨を報告したところ、警察に相談する形で届出するようにとの指示を受けて、同日中に、渋谷警察署に届出をしました(本件事故から1週間以上経過)。
(2)有印虚偽公文書作成罪に関する事実関係
患者Aの病理解剖は、同年2月12日(本件事故の翌日)午前9時半ころから、本件都立病院で病理解剖や検査等を主に担当していた医師が中心となって行われることとなりました。解剖終了後、医長と医師Cが院長室を訪れ、院長Xに解剖の説明をするとともに、患者Aの遺体の右腕の静脈に沿った赤い色素沈着を写したポラロイド写真を見せ、肉眼的な所見として、心臓疾患等が見られない旨告げました。その後、病理解剖を担当した医師も、院長室において院長Xに対し、心筋梗塞等、病死で死因を説明するようなものはなかった、血管が浮き上がっていた、血液がさらさらしていたなどと告げ、90%以上の確率で事故死であると思う旨の解剖所見を報告しました。 その後、同年3月10日、患者Aの夫が保険金請求のため、患者Aの死亡診断書、死亡証明書の作成を本件都立病院に依頼してきて、事務局長にその用紙を渡し、事務局長は、翌3月11日、これを主治医であった医師Cに渡してその作成を頼みました。医師Cは、病院内でその作成を始めましたが、死因として、不詳の死または外因死と記載するか、病死と記載するかで悩みました。その理由は、患者Aが死亡した直後の2月12日付けで、死因の種類を「不詳の死」とした死亡診断書を作成して、患者Aの夫に手渡していたところ、この時点では、病理解剖の所見などから病死を推認させるものは何もなく、むしろ、患者Aの右腕の色素沈着、看護婦が薬物を取り違えたことを認めていることなどから、事故死としか考えられない状況下であるのに対し、他方、事故死をこれらの書面に記載して保険金請求等に用いられることにより、病院が事故死を認めたことが公になり、病院に対する社会的非難が集中するのではないかと思いました。 そこで、医師Cは、自分個人の判断ではなく、病院全体の判断で決定して記載すべきことであると考え、院長Xに相談することにして、院長室に赴き、死亡診断書と死亡証明書の用紙を見せて、死因についてどのように記載するのが良いか聞いたところ、院長Xも、どうしたらいいかわからないなと悩んだ様子で、副院長ら及び事務局長を院長室に呼んで、どのように書けばよいかを話し合いました。その結果、未だ患者Aの血液検査の結果が出ていなかったこともあり、ヒビグルによる事故死と断定できないし、病死の可能性が0ではないので、病死としても全くの間違いではなく、入院患者について不詳の死とするのはおかしいなどとの発言もあったので、結局、死因として解剖の報告書に所見として急性肺血栓塞栓症といった記載があったので、死因を急性肺血栓塞栓症による病死として記載する旨その場の意見がまとまり、院長Xの指示で、医師Cは、死因を、外因死や不詳死ではなく、病死あるいは自然死であるとしました。具体的には、死亡診断書の「死亡の種類」欄の「外因死」及び「その他不詳」欄を空白にしたまま、「病死および自然死」欄の「病名」欄に「急性肺血栓塞栓症」と、「合併症」欄に「慢性関節リウマチ」等と記載し、死亡証明書の「死因の種類」欄の「病死及び自然死」欄に丸印を付する等して、死亡診断書、死亡証明書に記載し、これら書面を作成しました。その後、医師Cが作成した死亡診断書、死亡証明書は、3月12日に、事務局長から、患者Aの夫に手渡されました。
2 第一審判決(東京地裁平成13年8月30日判決)
(1)異状死の届出義務に関する事実関係
「医師Cは患者Aの主治医であり、患者Aは術前検査では心電図などにも異状は見られず、手術は無事に終了し、術後の経過は良好であって、主治医として患者Aについて症状が急変するような疾患等の心当たりが全くなかったので、H医師から、看護婦がヘパロックした直後、患者Aの容態が急変した状況の説明を受けるとともに、看護婦がヘパロックをする際にヘパ生と消毒液のヒビグルを間違えて注入したかもしれないと言っている旨聞かされて、薬物を間違えて注入したことにより患者Aの症状が急変したのではないかとも思うとともに、心臓マッサージ中に、患者Aの右腕には色素沈着のような状態があることに気付いており、そして、患者Aの死亡を確認し、死亡原因が不明であると判断していることが認められるのであるから、医師Cが患者Aの死亡を確認した際、その死体を検案して異状があるものと認識していたものと認めるのが相当である。」
「弁護人は、医師法二一条を本件のような医師が診療中の入院患者が医療過誤により死亡した場合に適用するのは許されないという趣旨のことを主張するが、医師法21条の規定は、死体に異状が認められる場合には犯罪の痕跡をとどめている場合があり得るので、所轄警察署に届出をさせ捜査官をして犯罪の発見、捜査、証拠保全などを容易にさせるためのものであるから、診療中の入院患者であっても診療中の傷病以外の原因で死亡した疑いのある異状が認められるときは、死体を検案した医師は医師法21条の届け出をしなければならないものと解するのが相当であって、弁護人の主張は失当である。」
(2)有印虚偽公文書作成罪について
「患者Aの手術は無事に修了し、術後の経過は良好であったのに看護婦が患者Aにヘパロックした直後、容態が急変して死亡し、主治医の医師Cが死体を検案し、そして、看護婦がヘパリンナトリウム生理食塩水と消毒液ヒビデングルコネート液を取り違えて患者Aに注入したかもしれないと言っており、死体の右腕には静脈に沿った赤い色素沈着があり、解剖所見も、死体には心筋梗塞等、病死で死因を説明するようなものはなく、被告人は、解剖を担当した医師から90パーセント以上の確立で事故死であると思う旨の報告も受けていたことが認められ、これら事実などにかんがみると、患者Aの血液検査の結果が出ていない段階においても、患者Aの死因が病死や自然死ではないことは明らかであり、そして、被告人(院長X)及び医師Cらは、これらの事実を認識していたのであるから、患者Aの死因を病死として死亡診断書、死亡証明書を作成することは虚偽の文書を作成することになり、かつ、被告人らは虚偽であるとの認識を有していたものと認めるのが相当である。 また、院長Xは、医師Cが死因の記載については個人の判断ではなく、病院全体の判断によるべきことであると考えて相談に来たのに対し、両副院長、事務局長の病院幹部を集めて協議した結果、医師Cに指示して患者Aの原因を病死として死亡診断書、死亡証明書を作成させたものというべきであって、被告人に右各書面の作成権限のあるC医師と共謀しての虚偽有印公文書作成、同行使罪がが成立すると認めるのが相当である。」
3 最高裁判決(最高裁平成16年4月13日判決)
「医師法21条にいう死体の「検案」とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わないと解するのが相当であり、これと同旨の原判断は正当として是認できる。 所論は、死体を検案して異状を認めた医師は、その死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、異状死体に関する医師法21条の届出義務(以下「本件届出義務」という。)を負うとした原判決の判断について、憲法38条1項違反を主張する。そこで検討すると、本件届出義務は、警察官が犯罪捜査の端緒を得ることを容易にするほか、場合によっては、警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることを可能にするという役割をも担った行政手続上の義務と解される。そして、異状死体は、人の死亡を伴う重い犯罪にかかわる可能性があるものであるから、上記のいずれの役割においても本件届出義務の公益上の必要性は高いというべきである。他方、憲法38条1項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解されるところ(最高裁昭和32年2月20日大法廷判決)、本件届出義務は、医師が、死体を検案して死因等に異状があると認めたときは、そのことを警察署に届け出るものであって、これにより、届出人と死体とのかかわり等、犯罪行為を構成する事項の供述までも強制されるものではない。また、医師免許は、人の生命を直接左右する診療行為を行う資格を付与するとともに、それに伴う社会的責務を課するものである。このような本件届出義務の性質、内容・程度及び医師という資格の特質と、本件届出義務に関する前記のような公益上の高度の必要性に照らすと、医師が、同義務の履行により、捜査機関に対し自己の犯罪が発覚する端緒を与えることにもなり得るなどの点で、一定の不利益を負う可能性があっても、それは、医師免許に付随する合理的根拠のある負担として許容されるものというべきである。
以上によれば、死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、本件届出義務を負うとすることは、憲法38条1項に違反するものではないと解するのが相当である。」
4 まとめ
(1)異状死体の届出義務について
本裁判例は、最初に述べたように、一般的には外表異状説を採用したものとして解釈されており、「平成16年の本判決後も,・・・医療界を中心とした本判決の解釈についての活動もあり,平成26年には,当時の田村憲久厚生労働大臣が,異状死体の届出義務につき,本判決を踏まえ『死体の外表を検査し,異状があると医師が判断した場合には,これは警察署長に届ける必要がある』と発言し(平成26年6月10日参議院厚生労働委員会会議録),平成27年度版マニュアルから,先の「『異状死ガイドライン』等も参考にしてください」との注が削除された。・・・以上のように,本判決以降も,様々な議論がなされてきたが,実務上は,本判決により,医師法21条の異状死体届出義務の前提となる死体の『検案』は,『医師が死因等を判定するために死体の外表を検査すること』であり,死体が発見されるに至ったいきさつ,死体発見場所,状況等諸般の事情は一切関係がなく,外表に異状がある場合のみを医師法21条に定める異状死体の届出義務の対象とすることが明確になった。」(医事法判例百選〔第3版〕・7頁・小島崇宏著)とされています。 一方で、学説においては、外表異状説には強い批判がなされており、「学説上は、既述のように同条の趣旨を刑事司法への協力義務と解することを前提に、『異状』性を極めて広く解し、明らかに犯罪性のない場合以外をすべて包含するものとする立場が通説である。」「近時、一部の弁護士(特に医療過誤事件を扱う弁護士)や医療関係者から、医師法21条の『異状』性は、死体の外表から『異状』と判断できる場合に限って肯定される、との見解(以下「外表異状説」と呼ぶ)が主張されるようになっている。この見解は、『異状』性の判断にあたり死亡に至る経緯を考慮しないとすることにより、医療過誤事例を要件解釈のレベルで一括して届出対象から除外することを意図するものであろう。・・・『異状』性の有無は、検案を行う医師が、死体の所見に加え、知りうる限りの過去の経緯や死体の発見状況などを総合的に考慮して判断するのであり、判断資料を外表から得られる情報に限定するとする外表異状説は不適切であると言わざるを得ない。学説上も、異状性判断で考慮されるの外表情報に限られないとする見解が有力である。外表異状説の論者は、上記平成16年最判の形式的な文言を自説の根拠とするが、この判決は『異状』性の判断については何ら一般的基準を提示しておらず、同説の根拠にはならないと言うべきであろう。」(米村滋人著『医事法講義』57頁、60頁)として、外表異状説に対して強く批判する意見も、学説では強いようです。 臨床の現場では、厚労省の見解と思われる外表異状説に沿って運用していくしかないと思いますが、外表異状説については、未だに、議論が収束していないという現状は認識しておいた方がよいかと思います。また、本来的には平成26年の医療法改正により導入された医療事故調査制度において、調査機関へ医療事故の報告を行うことで、医師法21条の届出義務を解除する立法が求められていました。しかし、平成26年の改正では、それが実現しませんでしたので、この点は、今後の立法課題であり、何らかの届出義務を解除する制度を実現することが期待されます。
(2)虚偽有印公文書作成罪について
本事案では、患者の死因について、医師らが協議の上、死亡診断書・死亡証明書に虚偽の記載をしており、当該行為について虚偽有印公文書作成罪が成立するとして処罰されています。「公文書」とは、「公務員が作成すべき文書」でありますが、東京都立広尾病院の医師は公務員として地位にあるため、公文書として処罰されています。 国立大学病院・独立行政法人国立病院機構・独立行政法人労働者健康安全機構・地方独立行政法人等に属する公的な病院には、「みなし公務員」規定が置かれており(国立大学法人法第19条等)、「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」とされています。したがって、これらの病院の医師が、診断書等に虚偽の記載をした場合も、虚偽公文書作成罪が成立しますので、絶対に虚偽記載をしないよう注意してください。
なお、みなし公務員とならない医療法人や個人が経営する病院(いわゆる「市中病院」)の医師であっても、「公務所に提出する診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をしたとき」は、虚偽診断書等作成罪(刑法160条)という別の犯罪が成立します。公的な病院であれ、市中病院であれ、犯罪が成立する場合があるため注意が必要です。