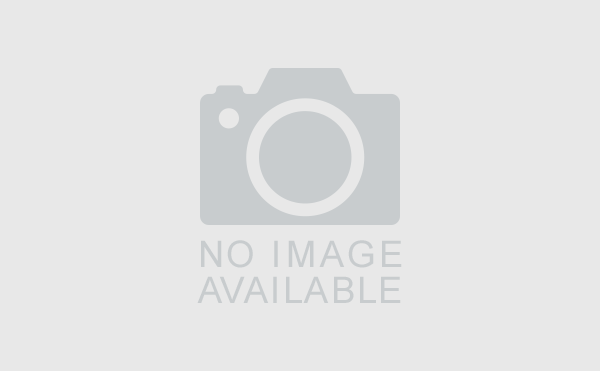No.174/医薬品添付文書に従わなかった医薬品(造影剤)投与について特段の合理的理由が認められた事例、 及び、医師の医療行為後の謝罪が医師の説明義務違反を推認させるものではないとされた事例 〜東京地方裁判所令和4年8月25日判決〜
Table of Contents
No.174/2025.5.1発行
弁護士 福﨑 龍馬
医薬品添付文書に従わなかった医薬品(造影剤)投与について特段の合理的理由が認められた事例、
及び、医師の医療行為後の謝罪が医師の説明義務違反を推認させるものではないとされた事例
〜東京地方裁判所令和4年8月25日判決〜
(はじめに)
医薬品添付文書に従わなかった医療行為の適否について、最高裁平成8年1月23日判決(以下「平成8年最判」といいます。)は、「医師が医薬品を使用するに当たって右文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」と判示しました(判例の事案の詳細については、本臨床医療法務だよりNo.14、108等を参照)。医薬品添付文書に記載された使用上の注意事項が医師の注意義務違反(過失)の有無を判断する際の規範となることを明らかにしたものですが、一方で、最高裁は、医薬品添付文書に従わないことについて「特段の合理的な理由」を主張立証できれば、「医師の過失は推定されない」ともしています。今回ご紹介する裁判例の事案は、うっ血性心不全の精査加療のため冠動脈造影検査を受けた患者に対し、造影剤を投与したところ、アナフィラキシーショックによって重度の後遺障害が残ったとして、患者が病院に対し損害賠償請求訴訟を提起した事案です。当該患者は、造影剤アレルギーの既往歴のある患者であり、添付文書上「禁忌」とされていました。判決では、医薬品添付文書の記載内容に従わない医薬品の投与があったが、従わないことに「特段の合理的な理由」があったとして、医師の過失は推定されないとの判断をしています。また、医薬品添付文書に従わない医薬品投与を行う場合の医師の説明義務の内容・程度を判示しています。さらに、本事案では、問題となっている医療行為(造影剤の投与)の後、担当医師は、説明義務違反を認めるかのような謝罪の言葉を患者家族に述べているのですが、道義的な見地から行った当該謝罪は、説明義務違反を推認させるものではないということも判示しています。
1 東京地方裁判所令和4年8月25日判決
(1)事案の概要
Xは、平成14年11月、不安定狭心症と診断され、Y病院に入院し、冠動脈造影検査(カテーテルから造影剤を流して冠動脈の状態を調べる検査。以下「CAG」という。)を受けたところ、左冠動脈前下行枝に99%の狭窄が認められ、経皮的冠動脈インターベンション(狭窄病変に対するカテーテル治療。以下「PCI」という。)を受け、上記狭窄が0%になりました。その後、Xは、平成15年5月にY病院でCAGを受けたところ、左冠動脈前下行枝に50%の狭窄が認められたが、他に有意な狭窄は認められませんでした。 その後、Xは、平成18年8月に胸痛が出現し、B病院で右冠動脈についてPCIを受けました。また、Xは、平成20年1月に不安定狭心症と診断され、Y病院に入院してCAGを受けたところ、右冠動脈等の狭窄が認められ、薬物治療を受けました。さらに、Xは、平成22年6月頃から胸部絞扼感を認め、これが改善しないため、平成23年1月に、Y病院に入院してCAGを受けたところ、右冠動脈等の狭窄が認められ、これらについてPCIを受けました。さらに、Xは、平成28年12月頃から労作時の息切れを自覚するようになり、平成29年2月28日にY病院で心臓超音波検査を受けたところ、LVEF(左室駆出率)が35%と低下していることが認められ、心不全に伴う二次性の中等度僧帽弁閉鎖不全と診断されました。そこで、Xは、平成29年3月3日、心不全の加療及び冠動脈の評価のためにY病院に入院し、同月9日、CAGを受けたところ、右冠動脈等の狭窄が認められました。このとき使用された造影剤はヨード造影剤であるイオメロンでした。Xは、イオメロン使用後、両手の掻痒感を訴え、その旨Y病院の診療録に記載されました。しかし、「《アレルゲン》」欄の使用された造影剤の名称は誤って「イオパーク」と記載されていました。Y病院の医師は、Xに軽度のアレルギー反応があったと判断し、XにPCIを行うに当たってステロイド前投与(造影剤使用に先立ってステロイド剤を投与し、アレルギー反応を抑制すること)を実施することとしました。Xは、同月13日、就寝前にステロイド剤であるプレドニン錠5mgを6錠服用し、翌14日正午、プレドニン錠5mgを6錠服用し、同日、イオメロンを使用してPCIを受けたところ、アレルギー反応は見られませんでした。 Xは、令和元年7月19日、Y病院を受診し、造影CT検査を受けました。このとき使用された造影剤はヨード造影剤であるオムニパークでした。Xは、オムニパーク使用後、結膜充血、両前腕の浮腫及び体幹発赤が見られ、造影剤アレルギーと診断されました。 Xは、令和元年8月末から安静時仰臥位で息苦しさを自覚するようになり、同年9月13日、C病院を受診して検査を受けたところ、両側胸水の貯留が認められました。Xは、同病院の紹介により、同月17日、Y病院を受診して心臓超音波検査を受けたところ、左室駆出率が20%と更に低下していることが認められ、心不全が憎悪したとして、同月18日、うっ血性心不全の精査加療のためにY病院に入院しました。Xの病床の上には「アレルギーあり ・オムニパーク ・イオパーク ・ヨード」と記載された紙が掲示されました。Y病院の医師は、Xにステロイド前投与を行った上でCAGを実施することとしました。Xは、同月24日の就寝前及び翌25日の朝、プレドニン錠5mgをそれぞれ6錠服用し、同日、CAGのため、造影剤としてイオメロンの投与を受けたところ(このイオメロンの投与を以下「本件投与」といいます。)、血圧低下(収縮期血圧50mmHg台まで低下)、呼吸状態の悪化が見られ、アナフィラキシーショックと診断されました。CAGは中止され、Xは、Y病院の集中治療室で、アナフィラキシーショックに対する処置として機械による呼吸補助、昇圧剤使用等の処置を受けました。その後、Xは、同月26日、一般病棟に転棟し、同年10月3日、Y病院を退院しました。
(2)判旨
ア 本件投与は注意義務違反といえるか
(ア)本件投与は医薬品添付文書に違反しているか
医師が医薬品を使用するに当たって、当該医薬品の添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される(最高裁平成8年1月23日第三小法廷判決参照)。本件投与がされた令和元年9月時点のイオメロンの添付文書には、「ヨード又はヨード造影剤に過敏症の既往歴のある患者」に対してイオメロンを投与することは禁忌と記載されていたところ、Xは、平成29年3月にヨード造影剤であるイオメロンの投与によって両手の掻痒感の症状が生じ、令和元年7月にヨード造影剤であるオムニパークの投与によって結膜充血、両前腕の浮腫及び体幹発赤の症状が生じたから、上記添付文書の「ヨード又はヨード造影剤に過敏症の既往歴のある患者」に当たる。しかし、Y病院の医師は、令和元年9月、Xに対してヨード造影剤であるイオメロンを投与し(本件投与)、その結果、Xはアナフィラキシーショックを起こしたから、上記添付文書の記載に従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、Y病院の医師の過失が推定される。そこで、本件投与をしたことに特段の合理的理由があったといえるか、検討する。
(イ)医薬品添付文書に従わなかったことについて「特段の合理的理由」があったといえるか
公益社団法人日本医学放射線学会の造影剤安全性管理委員会は、平成30年11月15日、「ヨード造影剤ならびにガドリニウム造影剤の急性副作用発症の危険性低減を目的としたステロイド前投薬に関する提言(2018年11月改訂版)」を発表した(この提言を以下「本件提言」という。)。本件提言の内容は、ヨード造影剤に対する中等度又は重度の急性副作用の既往がある患者に対しても、直ちに造影剤の使用が禁忌となるわけではなく、リスク・ベネフィットを事例毎に勘案してヨード造影剤の投与の可否を判断する必要があるというものであった。
本件提言は、急性副作用発生の危険性低減のためにステロイド前投与を行う場合には、緊急時を除き造影剤投与直前ではなく、充分前に行うのが望ましいとした。また、ステロイド前投与を行っても造影剤による副作用を完全に防ぐことはできず、副作用が再び発現することがあり、前投薬使用による経済的負担にも考慮する必要があるため、ステロイド前投与を行って造影検査を実施する場合には、事前に十分なインフォームドコンセントを得た上で、副作用発現時への対応を整えて実施することが望まれるとした。 ・・・本件提言を踏まえて、Y病院は、「ヨード又はヨード造影剤に過敏症の既往歴のある患者」に対してもリスク・ベネフィットを事例毎に勘案してヨード造影剤の投与の可否を判断していたほか、急性副作用発生の危険性低減のためにステロイド前投与を行うとともに、副作用発現時への対応を整えていた。 上記の認定事実によれば、イオメロンの添付文書には「ヨード又はヨード造影剤に過敏症の既往歴のある患者」に対してイオメロンを投与することは禁忌と記載されていたものの、実際の医療の現場では、本件提言を踏まえて、過去のアレルギー反応等の症状の程度、ヨード造影剤の投与のリスク及び必要性を勘案して、事例毎にヨード造影剤の投与の可否が判断されていたと認められる。そうすると、本件投与をしたことに特段の合理的理由があったか否かは上記事実を踏まえて判断するのが相当であり、過去のアレルギー反応等の症状の程度、ヨード造影剤の投与のリスク及び必要性等の事情を勘案してXに対して本件投与をしたことが合理的といえる場合には、上記特段の合理的理由があったというべきである。 ・・・本件提言は、中等度又は重度の急性副作用の既往がある患者に対してもリスク・ベネフィットを事例毎に勘案してヨード造影剤の投与の可否を判断する必要があるというものであるところ、Xに対しては心不全の原因を精査するために本件投与をする必要があったこと、Y病院の医師は、ステロイド前投与を行うことによってXにアレルギー反応等が生じる危険性を軽減することとし、さらに、本件投与で使用するヨード造影剤を、過去にイオメロン投与によってXにアレルギー反応等が生じなかった事実を踏まえてイオメロンにしたこと、加えて、Y病院では副作用が発現した時に対応できる態勢が整っていたことからすれば、Y病院の医師が本件投与によるリスクよりも本件投与の必要性が大きいと判断してXに対して本件投与をしたことは合理的であったというべきである。 ・・・本件投与をしたことには特段の合理的理由があったから、イオメロンの添付文書の記載内容に従わなかったことからY病院の医師の過失が推定されるとはいえない。
イ 説明義務違反の有無
医師は、検査を実施する場合、患者が自らの意思で当該検査を受けるか否かを決定することができるようにするため、患者に対し、病状、検査の内容、検査の必要性及び検査に付随する危険性を説明する義務を負っていると解されるところ、①Xは造影剤アレルギーと診断されていたこと、②造影剤によるアレルギー反応等として、非常に低い頻度ではあるが死亡等の重大な結果が生じることがあり得ること、③造影剤アレルギーの既往歴を有する患者に対する造影剤の投与は、添付文書上「禁忌」とされていることからすれば、Y病院の医師は、CAG及びこれに伴う本件投与の実施に当たって、Xに対し、病状、検査の内容、検査の危険性として造影剤投与のアレルギー反応等があること及びその危険性を踏まえてもCAGを実施する必要があることを説明する義務を負っていたというべきである。そこで、Y病院の医師らに上記の説明義務違反があったといえるか、検討する。 D医師は、令和元年9月17日、Xに対し、心不全が悪化して生命リスクの高い危険な状態であること、まずは心不全状態を改善するために早急に入院が必要であることを説明した。E医師は、同月18日、X、Xの長女及びIに対し、Xの造影剤アレルギーの既往を確認し、「治療・検査の説明書」と題する書面を用いながら、Xがうっ血性心不全であること及びその症状等を説明し、うっ血性心不全が改善した場合には、ステロイド前投与を行うことにより造影剤アレルギーの対策を講じた上で、心臓カテーテル検査の実施を検討することを説明した。 Y病院の医師は、同月24日、心臓カテーテル検査説明会を開催し、X及び他の患者に対し、本件説明書を配布した上で、一般的な検査の内容、合併症及び検査の流れに関するDVDを視聴させた。本件説明書には、心不全の病状、検査の目的や方法、検査の流れとして「冠動脈造影」の具体的な方法が記載されていた。また、合併症について、「時々見られる合併症」として、「血圧低下」、「発疹(造影剤や抗生剤のアレルギー反応)」等が、「比較的稀な合併症」として、「アナフィラキシーショック(造影剤や局所麻酔薬のアレルギー)」、「重症不整脈」、「死亡」等が記載され、合併症発生時の対応として、「【人工呼吸器】呼吸停止や心不全などで呼吸が十分保てない場合」が記載され、さらに、「検査により得られる情報の有用性…が、検査により起こりうる合併症の危険性よりも大きいと考えられる場合に、これらの検査…の適応があると判断されます」と記載されていた。E医師は、Xのベッドサイドに赴き、改めて、造影剤アレルギーの既往を確認し、Xに対し、ステロイド前投与を行うことを説明した。 上記の認定事実によれば、Y病院の医師らは、Xに対し、一連の説明により、Xの病状(心不全が悪化して生命リスクの高い危険な状態であること)、検査の内容(CAGの内容)、検査の危険性として造影剤投与のアレルギー反応等があること(合併症として発疹やアナフィラキシーショックがあること)及びその危険性を踏まえてもCAGを実施する必要があること(検査により得られる情報の有用性が検査により起こりうる合併症の危険性よりも大きいと考えられる場合に検査の適応があると判断されること及びステロイド前投与を行うことにより造影剤アレルギーの対策を講じること)を説明したということができる。したがって、Y病院の医師らに説明義務違反があったとはいえない。
ウ 本件投与の後、医師が患者の家族に説明不足を謝罪していた事実について
また、Xは、Y病院の医師が、令和元年10月2日にX及びその家族と面談した際に、「アレルギーがありながら造影剤を使用したこと」及び「説明が不足していたこと」を認めて「謝罪」し(Y病院の診療録)、同月7日にも改めて「検査前の造影剤アレルギーに対する説明が、不十分であったこと」を認めていることからすれば、Y病院の医師に説明義務違反があったことは明らかであると主張する。確かに、令和元年10月2日のY病院の診療録には、「予防対策をしながらの検査ではあったが、アレルギーがありながら造影剤を使用したことについて謝罪、説明が不足していたことの謝罪、アレルギー歴がある場合は家族も含めて説明をするよう改善する事をお伝えした」と記載され、同月7日のY病院の診療録には、「検査前の造影剤アレルギーに対する説明が、不十分であったことに対し、再度謝罪を行った」と記載されているが、既に認定してきた事実を総合すれば、上記謝罪は、Y病院の医師が、Xの家族(特にI)に対する説明が不十分であったと考えていたために道義的責任の見地から行ったものと認められる。よって、上記謝罪の事実によってY病院の医師に説明義務違反があったと認めることはできない。
2 まとめ(解説)
(1)医薬品添付文書に従わない医薬品投与とその説明義務
平成8年最判がある以上、医薬品添付文書に従わない医薬品の投与は原則行うべきではないし、仮に行う場合には、従わないことについて合理的な理由があるか、しっかりと検討しなければなりません。本件事案は、添付文書に従わない根拠として、学会の提言等をしっかりと検討し、リスクに備える体制が備えられていたため、添付文書に従わない医薬品投与が適法とされています。また、本裁判例は、添付文書に従わない医薬品の投与を行う場合は、通常の医療行為と比較して、より重い説明義務を課しているものといえます。禁忌とされている医薬品を投与するわけですから、医師は、当然、患者に対し、禁忌とされていていることや、禁忌なのに投与すべきと考える医学的根拠、メリット・デメリットをしっかりと説明しなければなりません。
(2)事故後の謝罪について
患者やそのご家族より、医療過誤を疑われて責任追及を受けており、一方で、医療行為の過失の有無が医療者自身でもまだ判断ができていないような場面において、医療者としては、率直に謝罪の言葉を述べるべきか、それとも、後々訴訟で不利になるから、謝罪の言葉は述べるべきでないか等、迷われることも多いかと思います。 事故後の「謝罪」の種類には、「“責任承認”という意味での謝罪」と、「“共感表明”という意味での謝罪」の2つがあるとされています。「責任承認としての謝罪」は、「自己の責任を認める意味での謝罪」であり、一方、「共感表明としての謝罪」は、「不利益を被った人への自然な共感的感情からくる“すまなさ”の感覚(“申し訳ない”という気持ち)を表明するもので、過失や責任と直接結び付くような意味合いは持たない。」と説明されています(例えば、「最善は尽くしたのですが、結果的に、このようなことになり申し訳ありません」などという表現が「共感表明としての謝罪」に当たります。つまり、本裁判例でいう「道義的謝罪」ということなのではないでしょうか。)。 少なくとも「共感表明」については、過失や責任と直接結び付くようなものではなく、むしろ医療事故に直面した人間の自然な行動として捉えられるものでありますから、これを躊躇する必要はないといえます。もっとも、「共感表明としての謝罪」をする場合には、そのことでは何も解決しているわけではないから、併せて「事実の解明やその報告」を約束し、そのことによって「再発防止」を約束することが肝要となります。 一方で、「責任承認としての謝罪」は、他の証拠と相まって過失判断の一資料とされる可能性があります。本件事案では、事故後、責任の所在が分かっていない早い段階で、医師が説明不足を認めて謝罪をしており、責任承認としての謝罪に近いものとなっています。本来であれば、この段階では、共感表明としての謝罪の趣旨を明らかにして、それにとどめておくべきであったといえます。しかし、それでもなお、裁判所は、他の証拠等を総合考慮のうえ、「事故後の謝罪は、医師の説明義務違反を推認させるものではない」と判断してくれていますが、実際の謝罪の仕方は拙劣で、責任を認めた趣旨での謝罪と受け止められかねません。謝罪の仕方については、きちんとどういう趣旨であるのか分かるように謝罪を試みることだと思われます。 事故後の原因究明ができていない時期であっても、共感表明としての謝罪は躊躇なく行うべきと言えますし、原因が究明され過失の存在が明らかとなった場合には、適宜適切な「責任承認としての謝罪」をためらうべきではないといえます。この段階での謝罪を拒否すると患者・家族の感情に不必要に火を付けること(医療者への不信感を増幅してしまうこと)になってしまい、その後の紛争が激化しやすくなります。「ためらい」によって適宜適切な謝罪の時期を逸失することは、取り返しのつかないボタンの掛け違えになることがありますので、事故後の適切なタイミングでの真摯な謝罪をためらわないようにすべきと考えます。