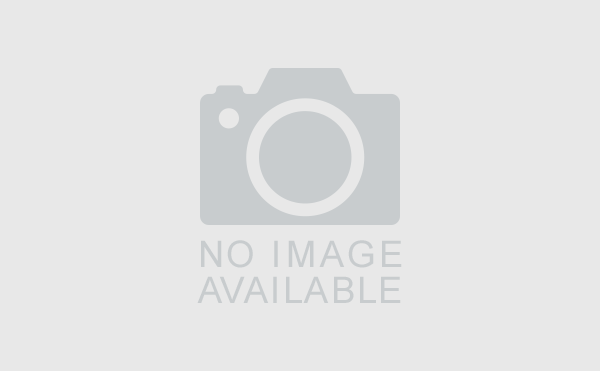No.176/裁判例にみる「説明義務違反と死亡・後遺障害との間の因果関係の可否」
Table of Contents
No.176/2025.7.1 発行
弁護士 福﨑 龍馬
裁判例にみる「説明義務違反と死亡・後遺障害との間の因果関係の可否」
(はじめに)
本稿では、インフォームドコンセント・説明義務を尽くしていないと判断されてしまった場合、医療者がどのような賠償責任を負うことになるのかについて、裁判例を踏まえながら見ていきたいと思います。臨床医療法務だよりでは、これまで、患者の状況・疾患の内容に応じて、医療者にどのような説明義務が求められるかについて、多数のレポートを出してきましたが、本稿は、‟その求められる説明義務を尽くしていないと裁判などで評価されてしまった場合”に、‟医療者が負う可能性がある法的責任”に関するレポートということになります。
1 基本的な考え方
(1)医療行為上の過失と説明義務違反との関係
患者が、医療行為によって亡くなったり、後遺障害を負う等した場合(医療行為の結果が、悪しき結果であった場合)に、医療訴訟においては、「医療水準を満たさない医療行為」に基づくものであったのか否かが争われることが多いといえます。一方で、‟説明義務違反と”いうのは、‟医療行為上の過失の存否”という争点と並行して、医療訴訟で争点化されることが多く、仮に、医療行為は適切であった(医療水準を満たしていた)としても、医療者が、患者に適切な説明をしていなければ、説明義務違反として不法行為ないし債務不履行を構成し、医療者は、患者に賠償責任を負うこととなります。
(2)医療行為上の過失と説明義務違反における損害の内容・額の違い
もっとも、説明義務違反による損害は、医療行為上の過失と比較すると、一般的には損害賠償の額は低いことが多いといえます。すなわち、医療行為上の過失による損害というのは通常は、患者の死亡や後遺障害等であり、その場合の損害の費目としては「逸失利益(将来得られたであろう収入)・慰謝料・治療費・介護費用」など様々なものが認められており、数千万円から数億円になることもあります。
一方で、説明義務違反の場合、通常は、死亡・後遺障害との因果関係が否定されることが多く、その場合の損害とは、適切な説明を受けて、自己決定をする機会を奪われたという「自己決定権の侵害」にとどまることとなるため、損害の費目としては、「慰謝料」だけしか認められません。そして、慰謝料というのも、あまり大きい額にはならず、数十万円から200万円程度を認める裁判例が多いようです。
(3)説明義務違反と死亡・後遺障害との因果関係が認められるための基準
ただし、説明義務違反と死亡・後遺障害との因果関係が認められた裁判例もいくつか存在しており、例えば、大阪地判平成17年7月29日は、「本件過失と本件患者の死亡との間に相当因果関係があるか否かは、被告担当医が本件説明義務を尽くしていたならば、‟本件患者が本件手術の実施に同意せず、本件手術が実施されなかったかどうか”によると解される」としたうえで、結論として因果関係を認めています。この場合には、損害は、単なる慰謝料では済まされず、医療行為上の過失における損害と同様に、数千万円から数億円もの賠償額になることもあり得ます。以下では、「2」において因果関係を認めた裁判例を2つ、「3」において因果関係を否定した裁判例を1つご紹介したいと思います。
2 説明義務違反と死亡・後遺障害との因果関係が認められた裁判例
(1)大阪地判平成17年7月29日(平成17年大阪地判)
ア 事案の概要
患者A は、嘔吐やめまいを訴えて、被告の運営する病院に救急搬送されたところ、頸動脈狭窄及び未破裂脳動脈瘤が発見された。そのため、患者A は、同病院において、未破裂脳動脈瘤をラッピングしてコーティングする手術を受けたところ、てんかん重積発作が発生した結果、遷延性意識障害となり、その後死亡しました。これについて、同人の妻及び子である原告らが、被告病院に対し、①患者A には、本件手術の適応がないのに本件手術を施行した、②本件手術について説明義務違反があった、③てんかん重責発作に対する予防及び発生後の処置に不適切な点があったなどと主張して、損害賠償を請求した事案です。なお、未破裂脳動脈瘤は、一度破裂してくも膜下出血を起こすと、半数ほどは死に至る危険な疾患ですが、一方で、破裂する可能性は年間1%程度と低いため、未破裂脳動脈瘤に対する治療は、必ずしも緊急性が高いとは言えない、予防的治療としての性質があります。そして、治療の必要性・緊急性が高くない医療行為について、裁判例は、医療者に対し、詳細かつ慎重な説明義務を求める傾向にあり、本裁判例においても、下記の通り、説明義務違反が認められています。
イ 判旨
(ア)説明義務違反
まず、説明義務違反について、「本件手術(未破裂脳動脈瘤につきラッピングしてコーティングする手術)は、本件患者の本件手術時の症状の消失・軽減を目的としたものではなく、本件動脈瘤の破裂を防ぐといういわゆる予防的手術という性格のものであって、本件動脈瘤に対して本件手術を実施することは、第一選択の治療法として、専門的研究者・医療者の間で一般的に是認された治療行為であるとまではいえないことからすれば、本件手術を実施しようというY担当医は、専門的研究者・医療者の間で一般に是認された治療行為を実施する場合に比して、より詳細かつ正確に本件手術の必要性、有効性及び安全性について、本件患者に対し説明すべき義務があるというべきである。・・・被告担当医は、本件患者に説明をしている事項もあるが、それ以外に、本件患者に対して、本件動脈瘤の生涯破裂率と本件手術において合併症が発生する可能性とが大まかにいって同程度であり、さらには左内頸動脈狭窄の状態からすると、本件手術をしないで、左内頸動脈狭窄の治療のために抗血小板剤を投与のみを実施するか、より詳しい検査を実施した上で、当面、特別な治療を行わず、経過観察を続行するという有力な選択肢があること、しかし、本件手術をしないで上記の選択をした場合には、上記のような問題点もあるので本件手術を実施するのが適切であると判断しているが、本件手術方法の破裂予防効果はクリッピング術に比べると、確実性が低い旨の説明をすべきであった(以下「本件説明義務」という。)のに、これを怠った過失(以下「本件過失」という。)があると認めることができる。」として、説明義務違反を認めました。
(イ)説明義務違反と患者の死亡との因果関係
「本件過失と本件患者の死亡との間に相当因果関係があるか否かは、‟被告担当医が本件説明義務を尽くしていたならば、本件患者が本件手術の実施に同意せず、本件手術が実施されなかったかどうか”によると解される。そこで、検討するに、上記のとおり、本件患者は、①被告担当医から、本件手術方法の破裂予防効果はクリッピング術に比べると、確実性が低いこと、②本件動脈瘤の生涯破裂率と本件手術において合併症が発生する可能性とが概ね同程度であり、③さらには左内頸動脈狭窄の状態からすると、本件手術をしないで、左内頸動脈狭窄の治療のために抗血小板剤投与のみを実施するか、より詳しい検査を実施した上で、当面、特別な治療を行わず、経過観察を続行するという有力な選択肢があること等の説明を受けていないところ、一般的な患者が、上記の説明を受けていれば、あえて開頭手術という重大な身体的侵襲を伴う医療行為を受けずに、左内頸動脈狭窄に対する抗血小板剤の投与という治療方法を選択するか、当面、特別な治療を行わず、経過観察を続行するとの選択をする者も相当数いるものと解される。
そして、本件患者は、④本件手術前の脳血管撮影の段階から同検査を嫌がり、さらには本件手術も嫌がっており、もし本件動脈瘤が破裂した場合はそれは運命なので仕方がないと考えていたのに対して、丁木医師が、本件患者や原告らに対して、上記のとおりの説明を怠ったばかりか、上記のとおり、⑤本件動脈瘤が破裂しやすいと誤解を与えるような説明や、左内頸動脈狭窄に対する抗血小板剤の投与が本件患者の本件手術前の症状の改善に必要であるかのような説明をして、積極的に手術を勧めたことにより、原告らが本件患者を説得した結果、本件患者が本件手術の実施を了承するに至ったことが認められる。以上によれば、被告担当医が本件説明義務を尽くしていたならば、本件患者は、本件手術の実施に同意せず、左内頸動脈狭窄に対する抗血小板剤投与の治療方法を選択するか、当面、特別な治療を行わず、経過観察を続行するとの選択をした高度の蓋然性があると認められる。よって、本件過失と本件患者の死亡との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。」
ウ コメント
上記の①から⑤の事情を考慮して、本裁判例は、説明義務違反と、患者の死亡との因果関係を認め、治療費・逸失利益・慰謝料等の合計3000万円を上回る損害賠償を命じました。
学説においては、説明義務違反と患者の死亡との因果関係の判断基準としては、①主観説と②客観説があるとされており、①主観説は、当該患者を基準にして、適切な説明がされていた場合、医療行為を受けていなかったといえるかで判断し、②客観説は、合理的な患者を基準にして、適切な説明がされていた場合、医療行為を受けたといえるかで判断するという、とされています(大島眞一裁判官「医療訴訟の現状と将来 最高裁判例の到達点」判例タイムズ1401号・69頁、藤山雅行裁判官「判例にみる医師の説明義務」新日本法規・12頁など)。本裁判例においては、因果関係を肯定するための考慮要素として、当該患者が、「仮に破裂したとしても、それは運命なので仕方がないと考えていた」という点が挙げられていることからすると、裁判例においては、当該患者を基準に、主観説で判断しているように読めそうです。大島眞一裁判官の上記論稿においても、「本来、当該患者について判断すべきことであるから、基本的に主観説が相当ということになるが、通常、合理的な患者の判断と一致するものと考えられる。」と述べられています。
(2)東京地判平成29年3月23日(平成29年東京地判)
ア 事案の概要
本件は、被告の開設するA歯科医院において左側下顎智歯(いわゆる「親知らず」のこと。)の抜歯術を受けた原告が、同手術の際に左舌神経が損傷され舌左側の知覚障害及び味覚障害の後遺障害を負うに至ったのは、被告に抜歯手技上の過失や説明義務違反があったからである等と主張して、被告に対し、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償の一部請求として、1850万余りの支払を求めた事案です。
すなわち、本事案は、「説明義務違反と後遺障害(知覚障害・味覚障害)との因果関係」が問題となった事案ということになりますが、その判断の仕方は、「説明義務違反と死亡との因果関係」の判断と同様のものになっています。
イ 判旨
(ア)説明義務違反
本裁判例は、「よって、被告には、抜歯以外の鎮痛剤・消炎剤等の投薬による本件智歯の保存という選択肢及び舌の知覚障害及び味覚障害の後遺症が残るリスクがあることについての説明義務違反があると認められる。」として説明義務違反を認めています。
(イ)説明義務違反と患者の後遺障害(知覚障害・味覚障害)との因果関係
「原告は、①一時滞在中のウィークリーマンションの管理人の紹介で、本件抜歯術当日に本件歯科医院を初めて受診したものであり、約10日後には東京の自宅へ帰宅する予定であったことや、②本件抜歯術を受ける前、「歯と口の治療管理」と題する書面の「歯の治療に対してあなたは」との質問に対し「すごく恐い」との欄にチェックを入れていることからすると、抜歯以外に鎮痛剤・消炎剤等の投薬による本件智歯の保存という選択肢があること及び抜歯に伴い舌神経の損傷による知覚・味覚障害のリスクがあることについて説明を受けていれば、本件抜歯術を受けなかったであろうと認められ、その結果、左舌神経の損傷による知覚・味覚障害の後遺症を負うこともなかったと認めることができるから、被告の説明義務違反と結果発生との間には因果関係が認められる。
なお、被告は、原告は、本件抜歯術の約2年6か月前に、当時仕事で数年間居住していた沖縄において右側下顎智歯に非常に強い痛みを感じ、同歯の抜歯を受けているが、その際に舌神経の損傷による知覚・味覚障害は生じておらず、また、本件智歯を抜歯しなかった場合にいずれ右側下顎智歯と同様の強い痛みを生じることも原告において予想されたことから、被告において知覚・味覚障害のリスクについて説明をしたとしても、原告が本件抜歯術を受けなかったとは考え難いと主張する。しかし、前記のとおり、原告は、本件抜歯術当日、ウィークリーマンションの管理人の紹介により本件歯科医院を受診したにすぎず、原告と被告との間に特別の信頼関係は形成されていなかったことや、原告は、約10日後には東京の自宅へ帰宅する予定であり、本件歯科医院に継続通院する予定もなかったことからすると、過去に右側下顎智歯の抜歯経験があったことをもって前記判断は左右されないというべきである。」
ウ コメント
以上の判断により、舌神経の損傷による知覚・味覚障害は、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当することを認め、休業損害・逸失利益・慰謝料等、合計529万円余りの損害賠償請求が認められました。この裁判例も、死亡事案と比べれば賠償額は低額ではありますが、説明義務違反が自己決定権の侵害にとどまる場合と比較したら、高額の賠償金が認められています。そして、本事案においても、一時滞在中の地で、たまたま訪れた歯科医院での治療であったことや、患者本人と歯科医院との特別な信頼関係の有無等、患者本人の主観的な事情を重要視していることが分かります。
3 説明義務違反と死亡との因果関係が否定された裁判例(東京地判平成4年8月31日・東大病院脳動静脈奇形(AVM)訴訟)(平成4年東京地判)
ア 事案の概要
29歳の女性Aは、頭痛のため、被告が設置する病院で診察を受け、昭和60年2月に、脳動静脈奇形(AVM)と診断されました。A は、過去に数回てんかん発作を起こしたことがありましたが、本件手術時には何らの神経脱落症状もなく、差し迫った危険はありませんでした。Aは、医師からその摘出を勧められたため、摘出手術を受けましたが、手術中に、著しい脳腫脹を引き起こし、2日後に死亡しました。A の家族である原告らは、被告に対し、AVM の手術自体の過失及び説明義務違反等を主張して、損害賠償請求訴訟を提起しました。
なお、このAVM は、先天性の血管奇形であり、脳内出血、クモ膜下出血などを引き起こす危険な疾患ですが、「AVMについて摘出手術をしなかった場合、出血によりA が死亡する危険性は年間およそ1パーセントであること、未破裂のAVM が出血した場合、死亡に至らなくても相当な後遺症を残す確率については十分な資料がないが、生存者のうちの二三パーセントであるとする報告がある」(平成4年東京地判から引用)とされており、未破裂脳動脈瘤に対する治療と同様、予防的治療と評価できます。
イ 判旨
(ア)説明義務違反
本判決では、原告らが主張する手術上の過失は全て否定したうえで、説明義務違反については、「医師は、原告らに対し飛行機事故の話をしたことについて、「飛行機に乗れば落ちる、外を歩けば交通事故に遭う、それと同じように手術にはそれ相応の危険がある。」という趣旨で話したものである旨証言する。・・・しかも、本件手術は、被告病院の実績でも過去5年間に40件中2件の死亡例があり、安全な手術と断定できるほどのものでもないのに、家族を安心させたいとの配慮かあったとしても、手術の危険性について飛行機事故の例を持ち出すなど、危険性がほとんどないに等しいと受け取られかねない表現を用いて説明しており、適切な説明を尽くしたとは認めがたい。・・・A は、本件手術の直前まで悲壮感も動揺もなく平然としており、原告らが本件手術の前日にAに会った際にも、担当医から「安全な手術だから何も心配はいりませんよ。」と説明を受けた旨述べたことが認められる。医師がA の家族である原告らに対してした説明内容や右の手術前のA の様子を総合すれば、担当医らは、A に対し、手術の危険性について、生命への危険性はないか、あるいは、ほとんどないに等しいという程度のことしか説明しておらず、手術の危険性と手術をしない場合の危険性を対比して具体的に説明するということもしていないものと推認される。・・・以上のとおり、担当医らは、本件手術に関して説明義務を負う相手方であるA に対し、手術の危険性や保存的治療に委ねた場合の予後について十分な説明を尽くさず、その双方の危険性を対比して具体的に説明することもしなかったのであって、このため、Aは本件手術を受けるかどうかを判断するために十分な情報を与えられなかったといわざるを得ない。」と述べて、説明義務違反を認めました。
(イ)説明義務違反と患者の死亡との因果関係
「原告らは、手術による生命の危険性について強い関心を抱いており、また、事前に相談した医師からは被告病院において手術を受けることについては消極的な助言を得ていたこと、A には幼い子供が二人あり、緊急に手術を要するほどの自覚症状は当時は発現していなかったこと等を考え併せると、担当医らが手術の危険性等について十分な説明をしていたならばA が手術を承諾しなかった可能性を全く否定することはできない。しかしながら、①手術を受けず保存的治療に委ねた場合の予後については、前述のとおり、出血して死亡する危険性は年間およそ1パーセントの確率であり、しかもA の余命は長く、死亡に至らずとも相当な後遺症を残す危険性もかなりの確率で存在した(右可能性は本件AVMが未破裂のものであることを前提としているが、前述のように、本件AVM
が出血を伴うものであった可能性を否定できず、その場合は更に危険性が高くなる)。しかも、②A は入院当初から手術をすることを覚悟していた形跡がある(前述のように、本件手術についての真に有効な承諾とはいえないが)。また、本件は、実際に開頭して手術を進めてみると予想外に癒着が強く、手術が困難を極め、結果的には不幸な帰結に至ったものの、③被告病院の設備とスタッフを考えれば、手術前にはそれほど高度な危険性を伴う手術とみることはできなかった。これらの事実を併せ考えると、A が担当医らから十分な説明を受け、手術にある程度の危険を伴うことを具体的に知らされたとしても、手術を承諾した可能性を否定することもできない。そうすると、担当医らがA に対して十分な説明をしておればA が本件手術を承諾しなかったかどうかは必ずしも明らかではなく、担当医らが必要な説明義務を尽くさなかったこととA が死亡したこととの間には相当因果関係があるとはいえない。」
ウ コメント
本事案では、手術の危険性はほとんどないに等しい程度の説明しかしていない、と認定されていることからすると、説明義務違反の程度は重いように思われますが、それにも関わらず、説明義務違反と死亡との因果関係は否定されています。そして、説明義務違反による自決定権の侵害として、慰謝料・弁護士費用として660万円のみを認めています。上記③において、因果関係を否定するための考慮要素として、「被告病院の設備とスタッフ」が挙げられていますが、被告病院は東京大学医学部付属病院であり、日本で最高峰の病院ということになります。これ以上の医療水準は存在しない可能性が高いため、どれだけ危険性を説明されたとしても、当該患者としては、当該病院で手術を受ける決断をした可能性が高いと判断されたのかもしれません。また、この点は、平成29年東京地判において考慮された、「患者と歯科医院との間の信頼関係」という考慮要素と共通する部分があるようにも思われます。すなわち、当該医療行為について高度な医療水準を有している医療機関や、日頃から通っている医療機関で医療行為を受ける場合は、患者と医療機関との信頼関係が築かれているため、医療行為の危険性を十分説明されたとしても、その信頼関係に基づき医療行為を受ける決断をする可能性は高いといえそうです。もっとも、私見としては、本件事案における説明義務違反の程度や内容からすると、説明義務違反と死亡との因果関係が認められる可能性は十分あった事案なのではないかという気がします。平成4年という少し古い裁判例でもありますので、過度に一般化するのは危険なように思われます。
4 裁判所の判断基準について
前述の大島眞一裁判官の論稿では、「まとめると、実施された療法が当該疾患では通常採られるものであった場合には、説明義務が尽くされていても、当該療法を選択したであろうと認めることができるので、死亡等の結果発生との因果関係が否定されることが多い。他方、未破裂脳動脈瘤の予防的手術や美容整形等については、危険性等の説明義務が不適切であった場合には、その説明義務が尽くされていれば当該手術を受けなかったといえる場合もかなり多いと考えられ、説明義務違反と結果発生との間で因果関係を認めることができる場合が少なくないと考えられる。」と述べられています。因果関係が肯定される可能性がある、未破裂脳動脈瘤の手術、美容整形、親知らずの抜歯というのは、いずれも、「必ずしも手術が必須ではなく、経過観察や他の治療法が選択肢として存在しているような医療行為、予防的医療行為」という性質を有しています。予防的医療行為や、経過観察等の他の治療法の選択肢がある治療を行うに当たっては、説明義務自体も重くなりますが、それだけでなく、仮に適切な説明を怠った場合には、それによって生じた死亡や後遺障害に関する賠償責任も負わなければならない可能性が高いということになります。このような医療行為を行うに当たっては、細心の注意を払って患者への説明義務を尽くす必要があります。