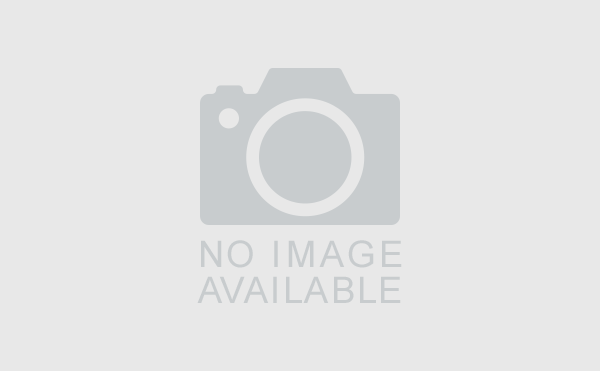No.167/裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その7 7.医療水準からして未確立な療法とその説明義務
Table of Contents
No.167/2024.11.15発行
弁護士 福﨑博孝
裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その7
7.医療水準からして未確立な療法とその説明義務
7.医療水準からして未確立な療法とその説明義務
(1)はじめに(医療水準と説明義務)
説明義務の範囲や程度は‟医療水準”と密接な関係にあり、患者の承諾を得る前提として病状、治療方法、その治療に伴う危険性等について、‟当時の医療水準に照らし相当と認められる事項(医療水準として確立した術式等)を患者に説明すべきである”とされています。したがって、原則論的には、「一般的にいうならば、実施予定の療法(術式)が医療水準として確立したものであるが、他の療法(術式)が医療水準として未確立のものである場合には、医師は後者について常に説明義務を負うとは解されない。」(平成13年11月27日(以下「平成13年最判」)といいます。)ということになります。
(2)未確立の術式であっても説明義務を負う場合
とはいえ、このような(医療水準に達していたとはいえない)未確立の術式ではあっても、医師が説明義務を負うと解される場合があることも否定できません。少なくとも、平成13年最判では、「①当該術式が少なからぬ医療機関において実施されており、相当例の実施例があり、②これを実施した医師の間で積極的な評価もされているものについては、③患者が当該療法(術式)の適応である可能性があり、かつ、④患者が当該療法(術式)の自己への適応の有無、実施可能性について強い関心を有していることを医師が知った場合などについては、たとえ医師自身が当該療法(術式)について消極的評価をしており、自らはそれを実施する意思を有していないときであっても、なお、患者に対して、医師の知っている範囲で、(ⅰ)当該療法(術式)の内容、(ⅱ)適応可能性や(ⅲ)それを受けた場合の利害得失、(ⅳ)当該療法(術式)を実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務がある。」と判示しています。要するに、本最判では、乳がん手術という特殊性を考慮し、「乳がん手術は、体幹表面にあって女性を象徴する乳房に対する手術であり、手術により乳房を失わせることは、患者に対し、身体的障害を来たすものであって、患者自身の生き方や人生の根幹に関係する生活の質にもかかわるものであるから、胸筋温存乳房切除術を行う場合には、選択可能な他の療法(術式)として乳房温存療法について説明すべき要請は、このような性質を有しない他の一般の手術を行う場合に比し、一層強まるものといわなければならない。」、「当該医師は、この時点において、少なくとも、当該患者の乳がんについて乳房温存療法の適応可能性のあること及び乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在を当該医師の知る範囲で明確に説明し、当該医師により胸筋温存乳房切除術を受けるか、あるいは乳房温存療法を実施している他の医療機関において同療法を受ける可能性を探るか、そのいずれの道を選ぶかについて熟慮し判断する機会を与えるべき義務があったというべきである。」と結論付けています。 本件事案は、患者が‟乳房切除術療法”について‟医師が説明をしなかったため術式選択の機会を奪われた”と主張した事案であり、平成13年最判が出る以前には、これを認める裁判例(大阪地判平成8・5・29、京都地判平成9・4・17)と、否定する裁判例(東京地判平成5・7・30、大阪高判平成9・9・19)に分かれていました。これら事例はいずれも乳房温存療法がわが国の医療水準上として確立された治療法とはいえないとされた時期(東京地判の例が昭和62年、京都地判の例が平成元年、大阪地判の例が平成3年)の手術に関するものであり、“医療水準として確立されていない治療法についても医師としては説明する義務あるのか”という問題が争点となっています。
(3)平成13年最判の類似事案としての福岡高判平成14・9・27
本件事件(最判平成13・11・27)の類似事案の判決として福岡高判平成14・9・27があります。この事案は、平成3年8月の時点で子宮頸がんの治療に当たり、子宮温存療法の希望を表明していない患者に対しても、その当時の最善の治療法とされていた子宮全摘術に加えて、未だ適応基準の確立していなかった治療的円錐切除術についての説明をすべきであったとして、医師の説明義務違反を肯定したものです。この福岡高判では、「子宮摘出という重大な身体侵襲行為についての患者の承諾は、治療効果の点で劣るものの子宮温存の治療法もあるということを知ったうえでなれなければ、治療をしないか子宮摘出かの二者択一になるとの誤解に基づくことになり、真の承諾とは言い難く、その意味で担当医師には治療的円錐切除術について説明する義務がある」とし、「子宮温存の希望を表明していない患者についても、内心でこれを希望していることも十分あり、その点を確かめるのにさしたる時間も手間もかからないから、これを確かめたうえで説明の要否を決めるべきであって、積極的に子宮温存の希望の表明がないということだけで医療機関が治療的円錐切除術の説明を怠った場合は説明義務違反となる。」としています。
(4)平成13年最判を更に敷衍した東京地判平成20・5・9
平成13年最判は、「医療水準に達した医療措置についての情報のみではなく、患者が希望しかつそれが患者の自己決定権に影響を及ぼす情報である場合には、説明義務の対象とする」との考え方を示しているものと思われます。これに沿う裁判例として東京地判平成20・5・9があります。この東京地判は、硬膜外麻酔を受けた患者に下肢の疼痛・痺れ等の症状が生じたことについて、同麻酔を施行した医師に、同麻酔の危険性等についての説明義務違反が認められた事案であり、「一般に、医師の説明は、患者が自らの身に行われようとする医療措置について、その利害得失を理解した上で、当該措置を受けるか否かについて熟慮し、決断することを助けるために行われるものであることからすれば、医師が、採用し得る複数の選択肢がある中で、患者の生命、身体に一定程度の危険性を有する措置を行うに当たっては、特段の事情がない限り、患者に対し、当該措置を受けることを決定するための資料とするために、患者の疾患についての診断、実施予定の措置の内容、当該措置に付随する危険性、他に選択可能な措置があれば、その内容と利害得失などについて説明すべき義務があると解される。また、上記の内容に含まれない情報であっても、患者が、特定の具体的な情報を欲していることを、医師が認識し又は認識し得べき状況にあった場合において、その情報が、患者が当該措置を受けるか否かを決定するに当たっての重要な情報である場合には、患者の自己決定を可能にするため、患者が欲している当該情報についても、説明義務の対象となるものと解するのが相当である。これを本件で行われた麻酔方法に関してみると、麻酔は患者の生命、身体に危険を及ぼすおそれのある措置であること、原告は麻酔に使用される薬剤についての不安を繰り返し述べていたことに鑑みれば、手術自体についての説明とともに、麻酔方法についても、説明義務の対象となるものというべきである。さらに、当該病院においては、手術前日に麻酔科医師が患者を診察した上で麻酔方法について決定するものとされていたことは前述とおりであり、本件においては、このことからも麻酔方法については説明義務の対象となることが首肯されるところである。」と判示しています。
(5)まとめ(SDMについて)
いまの臨床医療においては、「患者の自己決定権に裏付けられたIC」から更に「シェアード・ディシジョン・メイキング」(以下「SDM」)が重視されるようになっていますが、本件事案などはSDMが機能する場面かもしれません。医学・医療の知識に乏しい一般の患者、大病で精神が弱っている患者に、いくつかの複数の治療法から自らに合った治療法を選ばせることは容易なことではありません。そのような場面で必要とされるようになったのがSDMということなのですが、患者ひとり一人の生活環境や習慣・好み・思いを医師やその他の医療スタッフが共有し、病気や治療法に関しても十分に理解してもらった上で、その患者が最も納得できる最善の治療法を選択する手法であり、医療者と患者がエビデンスを共有して一緒に治療法を決定することになります。医療者にとっては、いままでのICにもまして大変な対応を強いられることになりますが、IC(情報提供)はSDM(意思決定支援)の中核をなすものであり、ICを深化させるものといえるかもしれません。