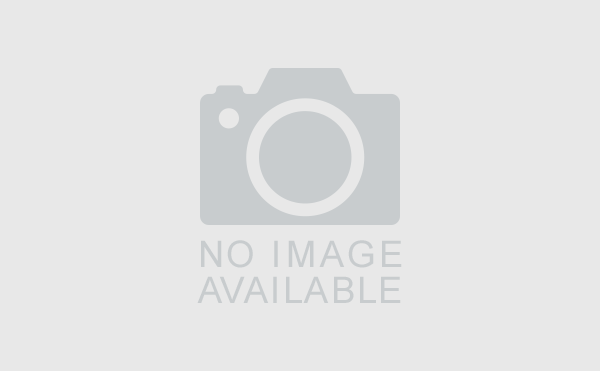No.166/裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その6 6.医療水準として確立された療法が複数存在する場合の説明義務
Table of Contents
No.166/2024.11.1発行
弁護士 福﨑博孝
裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その6
6.医療水準として確立された療法が複数存在する場合の説明義務
6.医療水準として確立された療法が複数存在する場合の説明義務
(1)医療水準に基づいた説明義務
医療水準が確立された療法が複数存在する場合については、最判平成13・11・27において、「医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合には、患者がそのいずれを選択するかにつき熟慮の上、判断することができるような仕方でそれぞれの療法(術式)の違い、利害得失を分かりやすく説明することが求められるのは当然である。」と判示しています。 また、同様の内容をさらに詳しく判示をするものに最判平成18・10・27(以下「平成18年最判」)があります。この事案では、未破裂脳動脈瘤について、「保存的に経過を見る」という選択肢(①)と「治療する」という選択肢(②)があり、「治療する」というばあいには、「開頭手術」(開頭して動脈瘤のけい部を永久的にクリップして閉じ、瘤に血液が流入しないようにする術式)という選択肢(②-1)と、「コイルそく栓術」(動脈瘤内にカテーテルでコイルを挿入して留置し、瘤内をそく栓する術式)という選択肢(②-2)があったが、そのいずれの選択肢も当時の医療水準にかなうものであったというものです。そして、本最判では、「医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務があり、また、医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合には、患者がそのいずれを選択するかにつき熟慮の上判断することができるような仕方で、それぞれの療法(術式)の違いや利害得失を分かりやすく説明することが求められる(最判13年11月27日参照)。そして、医師が患者に予防的な療法(術式)を実施するに当たって、医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合には、その中のある療法(術式)を受けるという選択肢とともに、いずれの療法(術式)も受けずに保存的に経過を見るという選択肢も存在し、そのいずれを選択するかは、患者自身の生き方や生活の質にかかわるものでもあるし、また、上記選択をするための時間的な余裕があることから、患者がいずれの選択肢を選択するかにつき熟慮のうえ判断することができるように、医師は各療法(術式)の違いや経過観察も含めた各選択肢の利害得失について分かりやすく説明することが求められるものというべきである。」と判示しています。 いずれにしても、この平成18年最判は、予防的な療法を実施するに当たって、医師は、①各選択肢の利害得失に関わる医学的知見のうち医療水準となっているものについては、説明を省略することは許されず、分かりやすく説明すべきである、②各選択肢に伴う危険の内容については、抽象的なレベルの説明では足りず、具体的に分かりやすく説明すべきである、また、③その上で、患者には熟慮する機会を与えるべきであると判示しており、予防的な療法を実施する場合の医師の説明義務について、相当に高い医療水準を求める姿勢を示すものといえます。
(2)平成18年最判後の同じ考え方に基づく裁判例
この平成18年最判は、医療水準として確立された療法が複数存在する場合の説明義務についてのリーディングケース(重要判例)とされ、その後の下級審の裁判例に多大な影響を与えており、ほぼ平成18年最判の判断に沿った内容となっています。
ア 名古屋地判平成23・2・18
本件は、患者が手術後に脳梗塞を発症し、左上下肢麻痺・高次脳機能障害が残った事案において、「医師は、患者の疾患の治療のために手術その他一定の合併症が発生するおそれがある医療行為を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務がある。その場合において、医療水準として確立した療法や術式が複数存在する場合には、医師は、患者がそのいずれを選択するかにつき熟慮の上判断することができるような仕方で、それぞれの療法や術式の違い、利害得失を分かりやすく説明することが求められる。」(平成18年最判参照)と判示しながらも、「脳動脈瘤の具体的な破裂率については、年1-2%より高いという具体的な説明がされており、経過観察とした場合の予後についても説明したと認めるのが相当である。また、本件手術により、重篤な後遺症(生命の危険が生じることもある)や術後麻痺、意識障害を起こす可能性があることについての説明はされていることから、術後麻痺等を引き起こす可能性のある脳梗塞についても説明がされたと認めるのが相当である。他方、未破裂脳動脈瘤に対しては、コイル塞栓術などの血管内治療もあるところ、本件全証拠をみても、当該医師が、未破裂脳動脈瘤に対しては、コイル塞栓術などの血管内治療という方法があることを説明したと認めるに足りる証拠はないが、原告の脳動脈瘤に対して血管内治療の適応があったということも認めることはできない。したがって、当該医師が説明義務に違反したと認めることはできない。」と判示しています。
イ 名古屋地判平成24・2・17
名古屋地判平成24・2・17は、平成18年最判の事案とほぼ同様の事案であり、本最判の判旨を引用した上で、「医師は、患者の疾患の診断、治療方法として開頭術又は血管内治療があること及びいずれの療法も受けずに経過観察をするという選択肢も存在すること、未破裂脳動脈瘤の年間破裂率は1パーセント程度とも2ないし3パーセント程度とも言われていること及び患者には破裂率を高める要因が存在することなどを説明し、自然経過の破裂率を考慮した上での治療の必要性についても十分に説明をしており、いつか破裂するのではないかという恐怖心から日常生活が制限される人もいること、医師としては経過観察を行い暫く観察するのがよいと思うが、患者の心配する気持ちを考えると治療するのもよいのではないかと思うことなども説明していることからすると、経過観察と積極的な治療(開頭術又は血管内治療)という選択肢の利害得失についての十分な説明はなされているというべきである。しかし、血管内治療と開頭術の比較において、医師は、血管内治療については、本件脳動脈瘤に血管内治療の適応があること、入院期間は開頭術よりも短いこと、治療自体も開頭術よりも低侵襲であり負担が少ないこと、コイルが瘤の中で上手く巻かないような場合は開頭術を行う場合もあることを説明した上、血管内治療に付随する合併症についても詳細な説明をしており利害得失について十分に説明をしている一方、開頭術については、全身麻酔が必要であること、術後に創部感染の危険性があること、入院期間は2週間程度必要であること、頭蓋骨陥没のリスクがあること及び抗けいれん剤を飲む必要があることといった開頭術における問題点の説明は十分になされているが、利点については、中大脳動脈の場合には技術的に血管内治療が難しい症例が多く、治療適応となることは少ないのに対して、開頭術は比較的容易であり、手術のリスクも高くなく、治療成績は良好であること及び手術の危険率や確実性の点から開頭術が選択される場合が多いことを説明しておらず、むしろ、開頭手術と血管内治療とで手術に伴う危険性は同程度であるという説明しかなされていない。以上によれば、医師は、開頭術又は血管内治療を選択するかにつき熟慮する上で重要な情報である開頭術の利点について十分な説明をしていなかったことが認められる。その結果、原告らは、開頭手術と血管内治療のいずれを選択するのかを熟慮する機会を与えられないまま、本件血管内治療を選択したといわざるを得ない。したがって、当該医師には、開頭手術の利点についての説明が不十分であった点において、説明義務違反が認められる。」と判示しています。
ウ 大阪地判平成24・3・27
本件は、未破裂脳動脈流に対するコイル塞栓術を受けた患者に術後正常圧水頭症が生じ、シャント術をうけたがなお高次脳機能障害が残存した事案において、‟コイル塞栓術の危険性について説明義務があったか否か”という点について、平成13年最判、平成18年最判の両最判の判旨を引用した上で、「A医師及びB医師は、未破裂動脈瘤に対するコイル塞栓術を実施するに当たり、患者に対し、患者の未破裂動脈瘤の状態(危険性や予後)、コイル塞栓術の内容及び合併症の危険性、医療水準として確立された他の療法である開頭クリッピング術及び保存的治療の内容、開頭クリッピング術及び保存的治療をコイル塞栓術と比較した場合の利害得失、予後の見通しについて、Xが熟慮の上で判断できるよう分かり易く説明すべき義務があると解される。そして、患者が、選択し得る各治療方法について、それぞれの利害得失を比較考量した上で、本件コイル塞栓術を受けるかどうかを判断するためには、コイル塞栓術を受けることによる危険性と、受けないで経過観察をすることによる危険性を比較することが必要であるが、それぞれの危険性どの程度の確率で発生するのかについて全く知らされない状態では、危険性を比較することは困難である。そうすると、A医師及びB医師は、少なくとも、本件動脈瘤の自然破裂率とコイル塞栓術の合併症の発生率について、当時有し又は有すべきであった医学的知見に基づき、できる限り具体的な数字を挙げて説明して、患者に対し、十分に考える機会を与えるべきであった。」と判示し、その上で、「そこで、A医師及びB医師の各説明についてみると、A医師及びB医師は、原告の未破裂動脈瘤の状態や、コイル塞栓術の内容及び合併症として頭蓋内出血や脳梗塞等が起こり得ること、合併症が生じた場合には致命的になる可能性があることについて、十分な説明をしたものと評価することができる。他方、A医師及びB医師は、Xに対し、本件動脈瘤の自然破裂率及び生存率、本件コイル塞栓術に伴う合併症の発生率、不完全塞栓に終わる危険性については説明していなかった。…したがって、A医師及びB医師には、未破裂動脈瘤の自然破裂の危険性とコイル塞栓術の合併症の発生率について、具体的な数字を挙げて説明を尽くさなかった点において、説明義務違反があったというべきである。」と判断しています。なお、A医師は、具体的な数字を挙げて説明しなかった点について、「確証ある数字ではなかったために、Xに告げなかった」と弁解しましたが、本判決は、「脳動脈瘤の破裂率や合併症の発生率に確証がなかったとしても、確証がないことを留保した上で、具体的な数字を挙げて説明することは可能であり、そのような留保付の説明であっても、患者の判断に資するものであったと考えられる。したがって、未破裂脳動脈瘤の自然破裂の危険性及びコイル塞栓術の合併症の発生率について、確かなエビデンスのある数値が明らかではなかったことを考慮しても、上記のように具体的な数字を挙げることは説明義務の内容に含まれる」と判示し、A医師の弁解をみとめませんでした。
(3)まとめ
以上のとおり、医療水準として確立された療法が複数存在する場合の説明義務に関する裁判例は、ほぼ平成18年最判をリーディングケースとしているといってよく、医師に対し、かなり詳細な説明を求める傾向が強いようです。特に、未破裂脳動脈瘤に対する予防療法などのように、リスクを伴う確立した予防的な療法がいくつか存在する場合には、裁判所は、自然破裂率・生存率、コイル塞栓術に伴う合併症の発生率などを数字で説明することを求めたり、あるいは、コイル塞栓術と回答術とのメリット・デメリットなどを細かく説明することをも求めています。