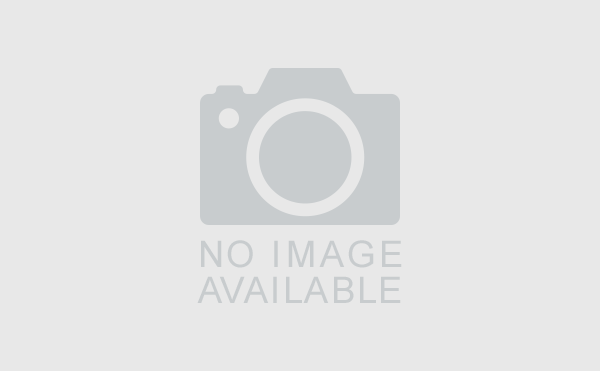No.165/裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その5 5.当時の医療水準と認められる事項を説明する義務(医療水準と説明義務)
Table of Contents
No.165/2024.10.15発行
弁護士 福﨑博孝
裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その5
5.当時の医療水準と認められる事項を説明する義務(医療水準と説明義務)
5.当時の医療水準と認められる事項を説明する義務(医療水準と説明義務)
(1)医療水準に基づいた説明義務
医師の説明義務の程度や具体性については、一般に、「医師は、緊急を要し時間的余裕がないなどの特別の事情がない限り、患者において当該治療行為を受けるかどうかを判断・決定する前提として、患者の現症状とその原因、当該治療行為を採用する理由、治療行為の具体的内容、治療行為に伴う危険性の程度、治療を行った場合の改善の見込み、程度、当該治療を受けなかった場合の予後について、当時の医療水準に基づいて、できる限り具体的に説明する義務がある。」(新潟地判平成6・2・10など)とされています。すなわち、医師の説明義務の範囲や程度については、当該療法に関する当時の医療水準との関係で理解されなければならず、さらには、緊急性や時間的余裕の有無、危険性の程度、患者の自己決定権の実質的保障など諸要素をも考慮して検討されなければなりません。このように説明義務の範囲や程度は「医療水準」と密接な関係があり、「医師が患者に対し手術のような医的侵襲を行うに際しては、原則として、患者の承諾を得る前提として病状、治療方法、その治療に伴う危険性等について、当時の医療水準に照らし相当と認められる事項を患者に説明すべきであり、右説明を欠いたために患者に不利益な結果を生ぜしめたときは、法的責任を免れない」(東京高判平成3・11・21)とされているのです。そして、ここにおいても、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」(最判昭和57・3・30、最判平成7・5・30)が問題とされ、それが説明義務の具体的な基準とされています(福岡高判平成16・12・1など多数)。したがって、医療水準として確立されていない治療方法については、原則として、「その方法の存在を前提とする説明義務はない。」ということになり(最判昭和57・3・30、最判昭和61・5・30、名古屋高裁金沢支判平成17・4・13)、最判平成13・11・27(乳房切除術事件)が判示するとおり、「一般的にいうならば、実施予定の療法(術式)が医療水準として確立したものであるが、他の療法(術式)が医療水準として未確立のものである場合には、医師は後者について常に説明義務を負うとは解されない」ということになります。
(2)具体的症例についての裁判例
ア 肝硬変治療に際し‟生体肝移植”について説明する義務(肯定)
大阪地判平成22・9・29は、‟肝硬変の治療に当たり生体肝移植について説明すべき義務の違反があった否か”が問題とされた症例なのですが、裁判所は、「生体肝移植の存在を前提にして重篤な肝硬変について検査・診断・治療等に当たることが、診療契約に基づき被告病院に要求される医療水準であり、また、不法行為における被告病院の担当医師の過失の基準としての医療水準でもあるところ、患者は重篤な肝硬変であり、平成17年3月22日以降は、内科的治療には限界があって早晩死を免れず、生体肝移植の適応があったから、当該病院の主治医である当該医師には、同日以降、少なくとも、当該患者あるいはその家族に対し、患者の肝硬変が重篤であり内科的治療では早晩死を免れないこと、唯一の根本的な治療法として生体肝移植があること、生体肝移植には当該患者に肝臓を提供するドナーの存在が必要であり、ドナーにも合併症が起こる可能性があること、生体肝移植には保険適用があること、生体肝移植をするか否かは最終的に当該患者本人及びドナー並びに家族が決めることを説明し、生体肝移植を実施するか否かを患者及びその家族に判断させるべきであったものと認められる。」、「しかし、本件診療期間中、当該医師は、当該患者やその家族に対し、患者の肝硬変の治療法として生体肝移植に言及したこと自体一切なく、この点において、当該医師を履行補助者とする当該病院につき診療契約上の説明義務違反があり、また、当該病院の被用者である当該医師に不法行為における過失がある。」と判示しています。すなわち、いまの裁判所は、肝臓疾患で生体肝移植の適用がある患者に対しては、そのこと自体を詳しく説明する義務を医師に課しているということができます。
イ 排卵誘発剤の投与に際し‟脳血栓症又は脳塞栓症の危険性(副作用)”を説明する義務(肯定)
福岡高判平成16・12・1は、‟大学病院における排卵誘発剤の投与に際し、副作用である卵巣過剰刺激症候群により発症しうる脳血栓症又は脳塞栓症の危険性やその症状”について、当時の医療水準及び担当医師の認識を考慮した上、医師の説明義務違反を認めています。すなわち、本判決では、「このような説明義務は、患者の自己決定の尊重のためのものであり、そのような危険性が具体化した場合に適切に対処することまで医師に求めるわけではないから、危険性が実現される機序や具体的対処法、治療法が不明であってもよく、説明時における医療水準に照らし、ある危険性が具体化した場合に生ずる結果についての知見を当該病院が有することを期待することが相当と認められれば、説明義務は否定されない。」と判示しています。すなわち、本判決では、治療行為自体を医師に求める場面ではありませんから、説明義務違反の前提となる医療水準は、治療行為の決定等の前提とされる医療水準と異なり、危険性が具体化した場合の結果についての知見(脳血栓症又は脳塞栓症の発症可能性)を当該病院が有することを期待することが相当であれば足りるとしてその説明義務を課しています。
ウ ERCP後膵炎による‟死亡の危険性”を説明する義務(否定)
長崎地佐世保支判平成18・2・20は、腹痛で入院した患者が内視鏡による膵管及び胆管の造影検査であるERCP(内視鏡的逆行性胆道膵管造影)を受けたところ、急性膵炎を発症し、検査の3日後に重症急性膵炎による多臓器不全で死亡した事案について、「当該医師は、‟ERCP後膵炎が重症化した場合に死亡の危険性があること”については説明していない。しかしながら、ERCP後に急性膵炎を発症して死亡する確率は、0.003%ないし0.0043%と極めて低いから、このような場合に死亡の危険性に言及しなかったとしても、医療行為を受けるか否かを自主的に選択する権利が害されるとはいえない。ERCPに関するインフォームド・コンセントを十分意識している医療機関においても、死亡の危険性にまでは言及されていないと認められるから、‟膵炎が重症化した場合に死亡する危険性があること”を患者に説明することが一般的な医療水準となっているとは解されない。したがって、当該医師には、ERCP後膵炎による死亡の危険性についてまで説明する義務があったとはいえない。」と判示しています。
エ 卵巣がん患者に(標準的治療法として未確立の)‟タキソール療法”を説明する義務(否定)
名古屋高裁金沢支判平成17・4・13は、「卵巣がんの治療に関する医学的知見に照らせば、タキソールは、卵巣がんに対する治療薬としては、平成9年12月に薬価収載されたばかりの新薬であり、そのため、タキソール療法は、平成10年1月当時において、卵巣がんに対する臨床での使用実績が少なく、その奏効率がCAP療法及びCP療法による化学療法との比較で優位であることの実証もされていない段階であって、卵巣がんに対する化学療法として未だ標準的な治療法となっていなかったこと、当該病院でも、卵巣がんに対する化学療法としてのタキソール療法についてはほぼ同様な状況にあったものであり、患者に対しては、CP療法後にタキソール療法が行われたが、それは、CP療法が副作用に反して奏効しなかったために2次的に選択された結果であったのであるから、医師には、平成10年1月当時において卵巣がんに対する化学療法として標準的な治療法であったCP療法を患者に対して実施するに当たって、患者からの特段の求めもないのに、‟未だ標準的治療法として確立していなかった治療法であるタキソール療法”について説明するまでの義務はなかったものというべきである。」と判示しています。