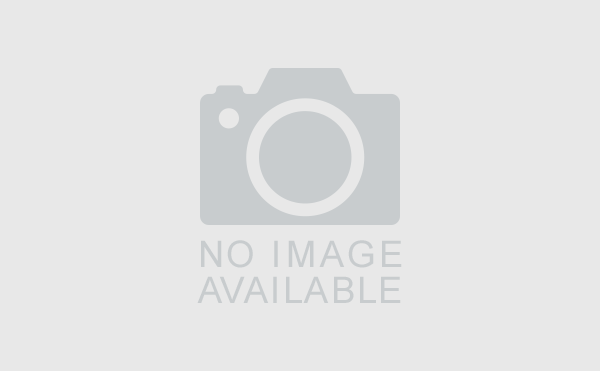No.164/裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その4 4.裁判例にみる‟説明義務の一般的内容”
Table of Contents
No.164/2024.10.1発行
弁護士 福﨑博孝
裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その4
4.裁判例にみる‟説明義務の一般的内容”
4.裁判例にみる‟説明義務の一般的内容”
医師が患者に対し負うべき説明義務とは、近時一般に、「医師が患者に対し、①病名、②病状とその原因、③治療行為の内容、④治療に伴う危険、⑤治療を行った場合の改善の見込み、⑥当該治療を受けなかった場合の予後、⑦代わりの治療行為、その場合の危険性、その改善の見込み、及び、⑧当該治療を選択した理由などを説明すべき義務」とされています。つまり、患者の自己決定に基づく正しい医療行為が行われるためには、医療機関が患者に関する情報を正しく認識した上で適切な説明をすることが不可欠なのです。この点について裁判例をみてみると、
(1)‟手術”を例にとって言えば、
最判平成13・11・27(乳がん乳房切除術事件)は、その説明義務の内容について、「(医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り)患者に対し、当該疾病の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務」と判示しており、これが‟最高裁レベルの医師の説明義務に対する現在の理解を示すもの”といわれています。また、横浜地判平成19・3・22では、「一般的に手術を行うためのインフォームド・コンセントの原則として、①病名、病状、②提案する手術の内容、③手術の必要性(手術をしない場合に病気がどう進展し、病状がどうなるのか)、④手術自体の危険性、⑤通常の術後の経過と入院期間、⑥術後に起こりうる合併症とその対策、⑦術後に生じる身体の変化と日常生活への影響、⑧勧める治療の効果、⑨他の治療法の可能性等が挙げられている」と判示していますが、これが判例・裁判例の一般的な考え方といえます。
(2)‟検査”を例にとって言えば、
名古屋地判平成16・9・30は、概ね「医師は、患者の疾患に対する適切な治療方針を立てるなどを目的として検査を実施しようとする場合、診療契約に基づき、患者に対し、その時点における疾患についての診断、検査の必要性、検査の内容、検査に伴う危険性などについて説明すべき義務を負うものと解される」と判示し、ほかの裁判例でもほぼ同旨となっています。すなわち、患者に医療行為の利害得失を知らせ、当該利用行為を受けるか否かについて熟慮の上で決定する機会を与える必要があることは、(特に危険性を伴う)検査を実施する場合も同様であり、手術に関する上記最判平成13・11・27の判旨が検査の場合にも基本的に妥当するということなのです。
(3)‟投薬による副作用”を例にとって言えば、
投薬による副作用について説明義務違反を認めた裁判例としては、高松高判平成8・2・27、東京地判平成16・3・12など数多くあります。例えば、高松高判平成8・2・27は、「医師には投薬に際して、その目的と効果及び副作用のもたらす危険性について説明すべき義務があるところ、患者の退院に際しては、医師の観察が及ばないところで服用することになるのであるから、その副作用の結果が重大であれば、発症の可能性が極めて少ない場合であっても、もし副作用が生じたときには早期に治療することによって重大な結果を未然に防ぐことができるように、服用上の留意点を具体的に指導すべき義務がある。すなわち、投薬による副作用の重大な結果を回避するために、服薬中どのような場合に医師の診察を受けるべきか患者自身で判断できるように、具体的に情報を提供し、説明指導すべきである。」と判示しています。また、東京地判平成16・3・12は、「オキシトシンが重大な副作用を生じうる危険性の高い薬剤であることからすれば、医師の患者に対する説明もより詳細なものが求められているというべきであり、患者の症状、オキシトシンの投与を含めていかなる治療手段があるか、投与方法、治療手段の危険性等について、概略を説明すべき法的義務がある。」と判示しています。また、広島地判令和2年1月31日は、「オキシトシンは胎児機能不全などの有害事象と関連性が示唆される薬剤であり、一度有害事象が発生すると、胎児に重篤な障害を生じさせるおそれのあるものである。したがって、医師は、オキシトシンについて、特段の事情のないかぎり、投与する必要性、手技・方法、高価、主な有害事象などについて説明をした後、患者から投与について同意を得なければその投与をしてはならないというべきである。」と判示しています。 もっとも、結果的には薬剤の説明義務違反を否定した裁判例もあり、大阪地判平成25・2・27は、「抗がん剤を投与してがんの治療を行うに際しては、当該抗がん剤を投与する目的やその効果のほかにその投与に伴う危険性についても説明すべきことは、診療を依頼された医師としての義務に含まれるものというべきであるが、その説明は、まずは、抗がん剤治療を受けるか否かを検討するにあたって一般的な患者であれば必要と考える内容の説明をすれば足り、患者がさらに詳細な説明を求めるなどする場合には、これに応じた適切な説明をすべき義務が発生するものというべきである。」と判示しています。いずれにしても、投薬による副作用についての説明義務の内容やその程度については、具体的に判断していくしかないということのようです。
(4)‟手術前の麻酔”を例にとって言えば、
東京地判平成20・5・9は、「医師が、採用し得る複数の選択肢がある中で、患者の生命、身体に一定程度の危険性を有する措置を行うに当たっては、特段の事情がない限り、患者に対し、当該措置を受けることを決定するための資料とするために、患者の疾患についての診断、実施予定の措置の内容、当該措置に付随する危険性、他に選択可能な措置があれば、その内容と利害得失などについて説明すべき義務があると解される。また、上記の内容に含まれない情報であっても、患者が、特定の具体的な情報を欲していることを、医師が認識し又は認識し得べき状況にあった場合において、その情報が、患者が当該措置を受けるか否かを決定するに当たっての重要な情報である場合には、患者の自己決定を可能にするため、患者が欲している当該情報についても、説明義務の対象となるものと解するのが相当である。これを本件で行われた麻酔方法に関してみると、麻酔は患者の生命、身体に危険を及ぼすおそれのある措置であること、原告は麻酔に使用される薬剤についての不安を繰り返し述べていたことに鑑みれば、手術自体についての説明とともに、麻酔方法についても、説明義務の対象となるものというべきである。さらに、被告病院においては、手術前日に麻酔科医師が患者を診察した上で麻酔方法について決定するものとされていたことは前述とおりであり、本件においては、このことからも麻酔方法については説明義務の対象となることが首肯されるところである。」と判示しています。
(5)‟患者に関する”正しい情報と、‟医療側に関する”正しい情報
確かに、患者が適切な自己決定をするには、まず‟自己(患者自身)に関する正しい情報”が必要となります。しかしさらに、そのためには‟自己に関する正しい情報”を、医師が認識し判断し得る人物か否かに関する情報も必要になるし、また、その医師が適切な医療行為をする能力を有するか否かに関する情報も必要となるといわれるようになっています。このように考えると、医師の説明すべき内容は、従来から指摘されてきた‟患者に関する情報”のみでは不十分であり、‟医師又はその所属する医療機関に関する情報”も必要ではないかと思われます。 例えば、福岡地判平成19・8・21は、「本件のような脳動脈瘤の手術方式として、体部クリッピング術とバイパス術+中大脳動脈瘤トラッピング術のいずれの方法がよいかを断定することはできず、いずれの方法を選択するかは、各医療機関の方針や術者の経験が重要な要素となることが認められる。…しかるに、当該医師は、脳外科の専門医であり日本脳神経外科学会認定医の資格を有しており、内頚動脈についてはバイパス術やトラッピング術を行った経験を有し、バイパス術自体も30例程度実施して経験を有しているが、バイパス術+中大脳動脈瘤トラッピング術を実施した経験を有していなかったところ、上記事実は、原告が本件手術を受けるか否かを決定するに当たり考慮すべき要素と解される。そうすると、上記事実が説明されなかったことは、本件手術の決定に当たり考慮すべき事項についての説明がなさ
れていなかったというべきである。以上によれば、当該医師は、原告が本件手術を受けるか否かについて必要な説明を怠り、原告の自己決定権を侵害したといわなければならない。」と判示しています。つまり、説明義務の対象となるのは「患者に関する情報」のみではなく、「当該医師及びその所属する医療機関に関する情報(経験・技量等)」も説明義務の対象とされつつあるということなのです。